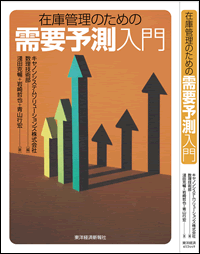初級編(発注業務編) 第3話 選べる満足、選べない不満 ~廃棄ロスと顧客満足度の関係とは~コラム
公開日:2021年4月15日

在庫削減や適正化など、多くの企業にとって重要な経営課題である需要予測・需給計画。
需給計画においては、コツやポイントを知らないままでいると、余計な作業負担や在庫過多といった問題に直面してしまいます。
そこで本コラムでは、はじめて需給担当者になった方やこれから需給について学びたい方向けに、需給計画の基本を分かりやすく解説します。
需給計画の中の発注業務をテーマに、発注業務の問題点と抑えておきたいポイントを見ていきましょう。
選べる満足、選べない不満
前回は、食品のように期限がある商品の場合、その期限を考慮した発注が重要である、ということをお話ししました。
今回は、顧客自ら『選べる』または『選べない』という状態が、顧客満足度にどのように影響するか、について考えてみたいと思います。
では、いつものように、お話の進行を『スーパーおおした』のおおした店長と、アルバイトのいろはさんに手伝ってもらいましょう。
顧客満足度と発注
ある日のバイト終わり。

-
いろは「お先でーす、失礼しまーす」
-
店長「おー、おつかれー!そうそう、いろはさん、前回のアドバイス通り、お弁当なんかを午前分と午後分に分けて発注するようにしたら、ほら、こんなに廃棄が減ったでー!」
-
いろは「わー、だいぶ減りましたねー。へー、お弁当はほぼ廃棄なしで、おにぎり系が売れ残ってる感じですねー」
-
店長「うんうん、ここ数日ずっとこんな感じで、廃棄も減ってよかったわー!」
-
いろは「え?ずっとですか?…でも廃棄減ってよかったです。じゃー、そろそろ帰りますねー」
-
店長「おー、気を付けてー!」
翌月のある日のバイト終わり。
-
いろは「お疲れさまでしたー、失礼しまーす」
-
店長「・・・おー、お疲れー・・・」
-
いろは「あれ?なんかヘコんでますねー。また廃棄が増えたんですか?」
-
店長「いや、廃棄はいつも通りやけど・・・。ほら、月次で集計している『お客さまの声』のアンケートあるやん?その結果がでたんやけど、お弁当コーナーの満足度が下がってて・・・賞味期限も考えて発注するように気を付けてたから、正直、満足度上がると期待してたのに・・・まさか下がるとは・・・ダブルショックで・・・なんでやろ?」
-
いろは「えー、そうなんですか?・・・そういえばちょっと前に気になってたんですけど、もしかして、毎日廃棄する商品って、だいたい決まってるんですか?」
-
店長「えっと、そうやねー。仕入れ単価の高いお弁当とかは、ほとんど廃棄がなくなって、廃棄ロスはほとんどなくなった感じかな?いつも廃棄になるのは、仕入れ単価の安いおにぎり系で、廃棄ロスも抑えられて良くなってるで?」
-
いろは「…店長、もしかしてそれが原因じゃないですか?」
-
店長「え?なんでなん?」
-
いろは「だって、お弁当やおにぎりを買うとき、複数の中から選びたいじゃないですかー?でもウチの店の場合、閉店間際に来たお客さんは、おにぎりしか選べなくなっちゃうんですよー?しかも、毎日ですよー?さすがに、『またおにぎりか、飽きたわー』ってなりませんかー?」
-
店長「…確かに…」
-
いろは「理想を言うと、『閉店間際にきたお客さんの好みに合う商品が、ある程度の選択肢を残した状態で陳列されている』のがいいんですかねー…だから、商品が完売するタイミングを考えて発注する量を調整したり、人気商品は少し多めに発注したりするのがいいのかな…?わかんないですけど」
-
店長「…なんかそんな気がしてきた…。そうなってくると、ちょっと棚割り※1も考えんとなー…ちょっと考えてみるわー…」
解説
皆さんはどうですか?お弁当を買いに行ったとき、選択肢が全くないのは困りますよね。
廃棄を伴う商品を取り扱う経営者にとって、『廃棄ロス』も『顧客満足度』も重要なKPIになりますが、この2つのKPIはトレードオフの関係になりがちです。おおした店長は廃棄ロスというKPIのみを評価指標にしていたため、顧客満足度を考慮できていませんでしたが、本来はバランスよく考えていく必要があります。
ネット通販の場合、陳列しなくても売ることがでるため、ニッチな商品でもたくさん取り扱うことで顧客満足度を上げ、かつその販売総額がヒット商品の販売総額を上回ることもできます(これを『ロングテールの法則』と呼びます)が、スーパーはネット通販とは違い、モノが並んでないと売れません。そこで重要になってくるのが、品揃えと棚づくりです。
品揃えは、MD(マーチャンダイジング)と呼ばれる、『適正な商品』を『適正タイミング』に『適正な場所』で『適正量』かつ『適正価格』で提供するための計画によって決定することができます。
また、今回のようなスーパーの場合、大手家電量販店のように販売員がいて接客するような形態ではないため、顧客自らに価格や商品の魅力を判断してもらい、購入へ導く必要があります。そこで重要になってくる一つの要素が棚づくりですが、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)と呼ばれる手法を使うことで、商品を陳列して演出する際に、顧客に対して視覚的にMDを訴えることができるようになります。
『廃棄ロスが少なければいい』『モノがあればいい』ではなく、廃棄ロスも顧客満足度も、どちらもバランスよく適正化していくことが重要ですね。
最後にもう一つ、こういう事例があります。とある店舗のおにぎりの需要予測精度が異常に良かったので調べてみたところ、予測10個、仕入れ10個、販売10個、という状態だったことが分かりました。つまり、実際は品切れしており、機会損失が発生していたわけです。計算上は予測誤差0になりますが、これでは本当の意味で予測精度が良いとは言えませんよね。そこで、POS※2データから最終販売時刻を抽出して、『もし品切れしていなけば売れていたであろう数量』を推定し、その数量を使って予測するように改善しました。今回の例でも、いろはさんは『人気商品は少し多めに発注したりするのがいいのかな…?』って言っていたので、何となくボンヤリとは気づいているようですが、この事例のように改善できるようになるには、もうすこし時間がかかりそうですね。
次回の第4話では、もうすこし詳しく『需要予測と発注』についてお話ししたいと思います。
-
※1
棚割り…どの商品をどこに、どれくらいの列(フェイス)陳列するか計画すること
-
※2
POS…Point Of Salesの略で、販売時点情報管理のこと
【需給初心者向けコラム】の記事一覧
初級編(発注業務編)
初級編(需給業務編)
初級編(番外編)
初級編(調達業務編)
筆者紹介
- 大下 吾朗(おおした ごろう)
-
R&D本部 数理技術部 シニアコンサルティングスペシャリスト
米国PMI認定プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル。
需要予測・需給計画ソリューション FOREMAST(フォーマスト)の開発およびシステム導入プロジェクトに従事。
主に在庫補充量計算に関する機能設計・開発を担当。
関連書籍など
在庫管理のための需要予測入門
FOREMAST担当コンサルタントが執筆した需要予測入門書です。
どのような需要予測システムを導入すればよいかお悩みの方のために、実務に精通したコンサルタントが基本知識からシステム導入時に考慮すべきポイントまでをやさしく解説しています。
在庫管理のための需要予測入門
キヤノンシステムソリューションズ株式会社数理技術部[編]
淺田 克暢+岩崎 哲也+青山 行宏[著]
- 出版社:東洋経済新報社
- 発売日:2004年12月22日
- ISBN:4492531874
- 価格(税込):1,980円
関連するソリューション・製品
- FOREMAST
- 大量の在庫を抱えているのに欠品や納期遅れが発生していませんか?「キャッシュフロー経営」が叫ばれる中、多くの企業で在庫削減が重要な経営課題となってきています。しかし一方で、お客さまからの即納・短納期要求は益々強くなってきており、欠品の発生が企業経営に大きな影響を与えるケースも増えてきました。FOREMASTは、科学的な需要予測に基づく在庫補充計画と、需給計画・実績情報の共有支援、問題の見える化により、欠品なき在庫削減の実現を支援します。