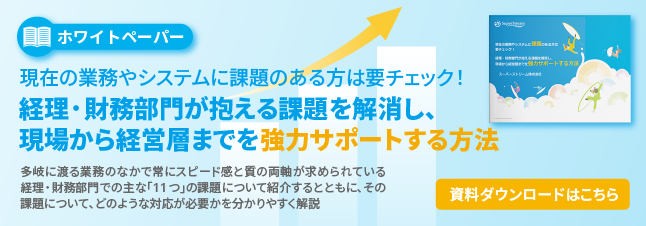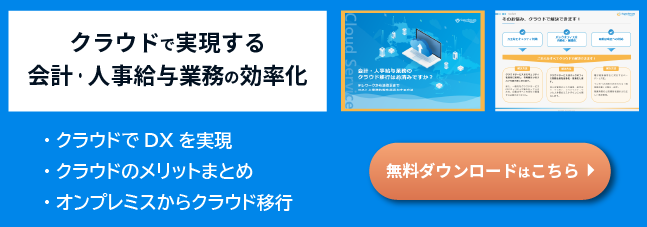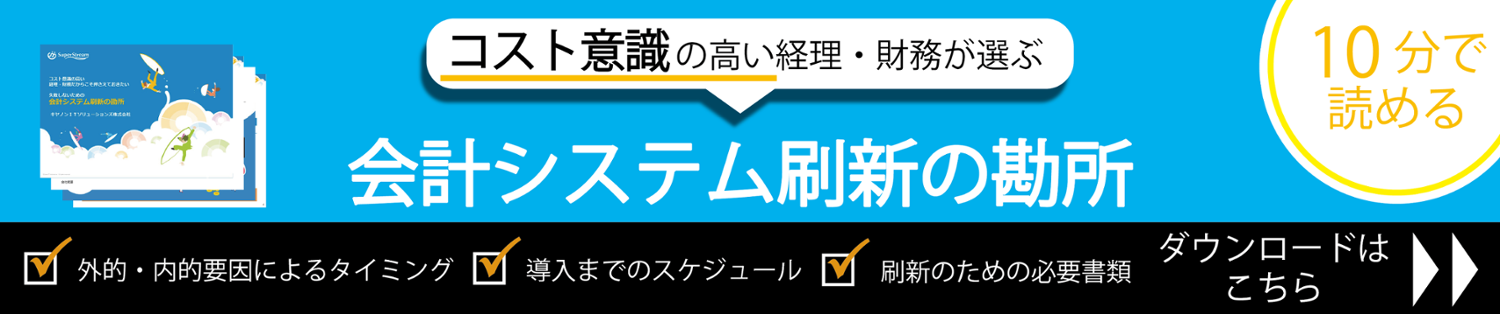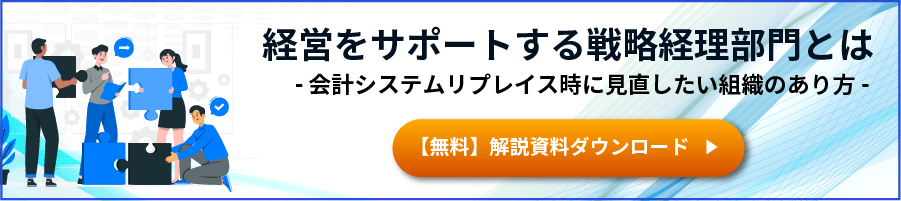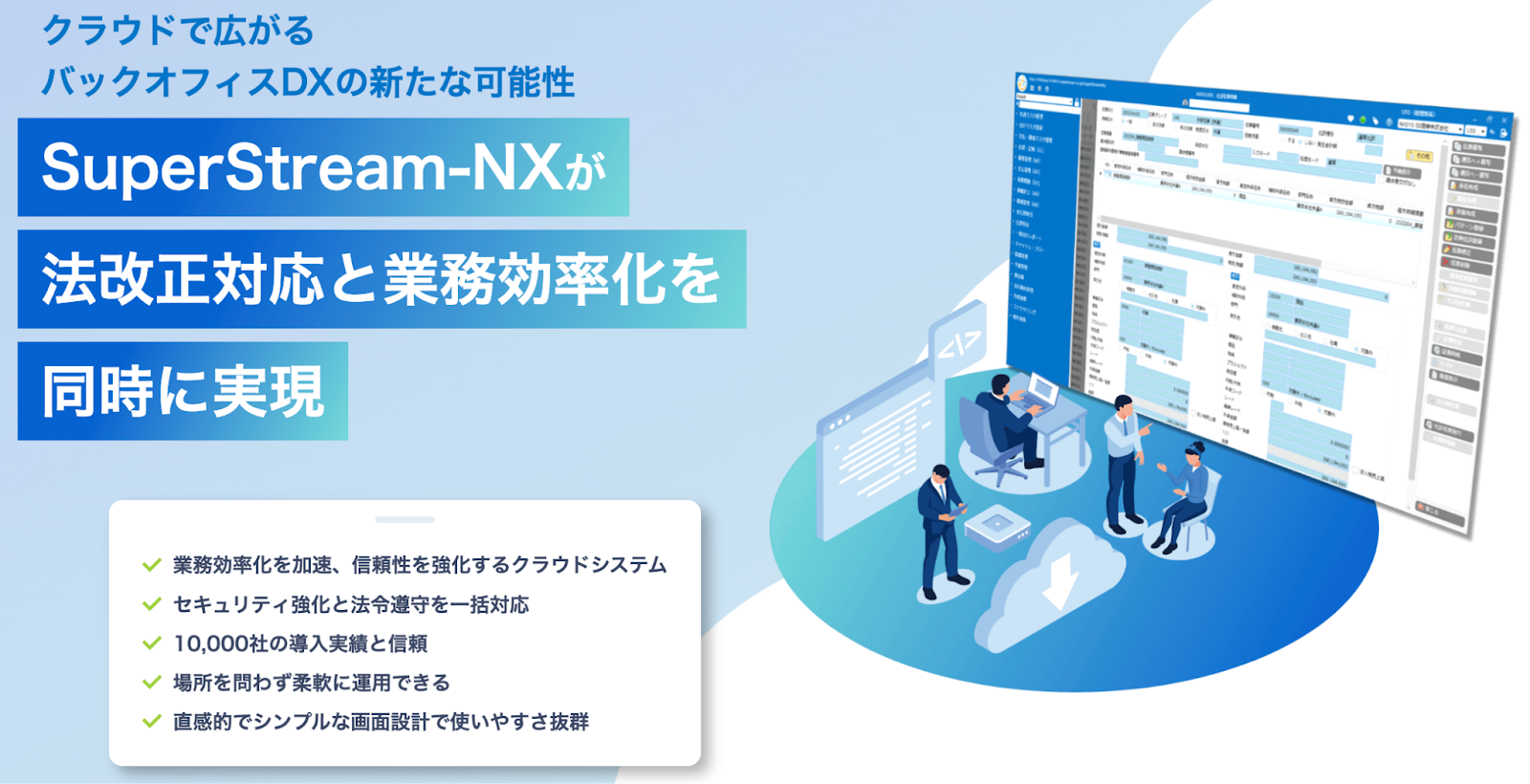請求書の支払業務を効率化するデジタル化と自動化の流れを徹底解説トレンド情報
請求書の支払業務を効率化するデジタル化と自動化の流れを徹底解説トレンド情報
公開日:2025年7月16日
紙や手作業による請求書の支払業務は、ミスや業務負担の増加を招く要因です。デジタル化と自動化の流れが進む中、最新のシステムを導入することで、入力や確認作業の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの削減や内部統制の強化も実現可能です。そこで今回は、請求書の支払業務を効率化するデジタル化と自動化の流れを徹底解説します。ぜひ参考にしてください。
請求書支払業務のデジタル化が求められる背景
請求書支払業務のデジタル化が求められる背景として、主に次の3つの要因が挙げられます。
法改正と電子帳簿保存法対応の必要性
2022年1月から施行された電子帳簿保存法の改正により、請求書など国税関係帳簿書類の電子保存が求められるようになりました。
改正電子帳簿保存法では、受領した請求書の電子保存が義務化された部分もあり、企業では紙の書類管理から電子データでの保存・管理へ移行する必要性が高まっています。
この法令対応が、請求書支払業務のデジタル化を後押ししています。
インボイス制度とペーパーレス化の推進
インボイス制度の導入により、請求書には適格請求書発行事業者登録番号や税率ごとの区分記載など、法定要件を満たした情報管理が求められるようになりました。適格請求書を紙ベースで運用するのは煩雑でミスも起こりやすいため、電子化による自動チェックやペーパーレス化が強く推進されています。
電子請求書システムの導入によって、承認や保存もクラウド上で完結し、オフィススペースや印刷コストの削減、テレワーク対応など多くのメリットが生まれています。
DX推進による経理業務の変革
労働人口の減少や人手不足が深刻化する中、経理部門でも業務の効率化と生産性の向上が強く求められています。
グローバル競争や市場変化への即応力を高めるためにも、経理業務のデジタル化は不可欠な要素といえるでしょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、請求書支払業務のデジタル化は、業務の属人化や手作業によるミスや承認遅延といった課題を解決し、迅速な経営判断や内部統制の強化、コスト削減にも直結する重要な取り組みです。
下記の資料では、多岐に渡る業務のなかで常にスピード感と質の両軸が求められている経理・財務部門の主な「11の課題」について、どのような対応が必要かを分かりやすく解説します。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
請求書支払業務の現状と課題
次に、請求書支払業務の現状と課題について解説します。
手作業や紙運用による非効率性の高さ
多くの企業では、請求書の受領から支払処理まで紙ベースや手作業で行われており、これが業務の大きな非効率要因となっています。
紙の請求書は郵送やファイリングに時間とコストがかかり、担当者の負担も増加します。さらに、テレワーク環境では紙の管理が難しく、業務の停滞や遅延が生じやすいです。
こうした非効率は経理部門の生産性低下や人的リソースの逼迫を招き、DX推進の妨げにもなっています。
入力ミスやヒューマンエラーのリスク
手入力による請求書データの転記は、誤入力や金額の見落としなどヒューマンエラーの温床です。特に複雑な税率区分やインボイス制度対応の項目が増えたことで、ミスのリスクがさらに高まっています。
これらのミスは支払遅延や誤払い、監査指摘の原因となり、企業の信用や財務健全性に悪影響を及ぼす要因です。そこで、AI-OCRなどの自動化技術導入が急務とされています。
業務属人化とガバナンスの課題
請求書支払業務が特定担当者に依存すると、担当者不在時の業務停滞や引継ぎミスが発生しやすくなります。また、承認フローやチェック体制が曖昧だと、不正支払いや不適切な支出のリスクが高まります。
上場企業や大手企業では内部統制の強化が求められており、ガバナンス面の課題解決が急務な状況です。そこで、システム化による業務の見える化と標準化を図ることが重要なのです。
下記の資料では、経理・財務部門と情報システム部門の方たちに向けて、リプレイス時に組織全体を見直す戦略的アプローチを提案しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
デジタル化・自動化による請求書支払業務効率化のプロセス
以下では、デジタル化・自動化による請求書支払業務効率化のプロセスを3つに分けて解説します。
1.AI-OCR・RPAによるデータ入力自動化
AI-OCRを活用することで、受領した紙やPDFの請求書から取引先名や金額、日付などの情報を自動でデータ化できます。また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)と組み合わせることで、会計システムへの入力や支払予定表の作成、仕訳起票などの繰り返し作業も自動化が可能です。
これにより手入力の手間やヒューマンエラーが大幅に削減され、業務の正確性とスピードが向上します。
2.電子請求書の受領・保存フロー
取引先から電子請求書を受領し、システムにアップロードすることで、紙の保管や郵送が不要となります。電子帳簿保存法対応のシステムを使えば、請求書データを法令に準拠した形で安全に保存・管理でき、検索や証憑提出もスムーズです。承認フローもデジタル化されるため、リモートワークや多拠点運用にも柔軟に対応できるのが大きなメリットです。
3.システム連携による一元管理
請求書管理システムと会計システムやERP、銀行振込システムなどを連携させることで、請求書の受領から支払い、仕訳、消込、証憑保存までの一連の業務を一元管理できます。
これにより、Excelや紙での個別管理が不要となり、債務残高や支払状況をリアルタイムで可視化することが可能です。また、業務の属人化を防ぎ、ガバナンスや内部統制の強化にもつながります。
下記の資料では、累計11,000社以上が導入している「経理部・人事部ファースト」の思想に基づいて開発された、圧倒的な使いやすさを実現している「SuperStream-NX Cloud」について解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
請求書支払業務を自動化するシステムの導入ステップ
以下は、請求書支払業務を自動化するシステムの導入ステップです。ぜひ参考にしてください。
1.現状業務フローの可視化と課題整理
まず、自社の請求書支払業務の現状を詳細に把握し、受領から承認、支払、保存までの各工程を可視化します。
どの工程で手間やミスが多いか、どこにボトルネックがあるかを明確にし、業務量や担当者の負担、発生しているエラーやコストなどを定量的に整理しましょう。
これにより、自動化による改善効果が期待できるポイントや必要な機能要件が明確になります。
2.システム選定と導入計画の立案
次に、自社の課題や業務フローに合致した請求書自動化システムを選定します。
AI-OCRやワークフロー自動化、会計システム連携など必要な機能を比較し、コストやサポート体制も考慮しましょう。
導入計画では、初期設定や既存システムとの統合、承認フローや権限設定、取引先への周知・協力依頼など、移行手順を具体的に策定することが大切です。
3.定着化・運用改善のポイント
システム導入後は、現場担当者への操作説明やマニュアル整備、トレーニングの実施が不可欠です。
まずはスモールスタートで効果を検証しながら段階的に拡大し、現場の声をもとに運用フローや設定を見直しましょう。
定期的なメンテナンスやエラー対応、継続的な改善活動を行うことで、システムの定着と長期的な効率化を実現します。
下記の資料では、経理・財務部門が日常利用する会計システムの刷新タイミングと、刷新時のステップとポイントを押さえつつ、「SuperStream-NX」を活用した際のメリットを具体的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
請求書支払業務自動化システムの選び方のポイント5つ
次に、請求書支払業務自動化システムの選び方のポイントを5つ挙げて解説します。
1.自社の課題と目的に合わせる
請求書支払業務自動化システムを選ぶ際は、まず自社の現状業務フローや課題、導入目的を徹底的に洗い出すことが重要です。どの工程で手間やミスが多いのか、何を効率化したいのかを明確にすることで、必要な機能やサービスの優先順位が定まります。
2.AI-OCR精度やデータ化対応範囲の確認
AI-OCRの文字認識精度や、明細行ごとのデータ化対応範囲を必ずチェックしましょう。請求書の書式や内容が多様な場合、AI-OCRの精度が低いと手作業が残り、十分な効率化が図れません。事前にサンプル請求書でテストできるかも確認しましょう。
3.会計システム等との連携性
既存の会計システムやERPとの連携がスムーズにできるかは極めて重要です。APIやCSV連携、仕訳自動作成など、データの一元管理や転記ミス防止につながる機能が備わっているかを重視しましょう。
4.セキュリティ・サポート体制
請求書には機密情報が多く含まれるため、データ暗号化やアクセス権限管理、監査ログなどのセキュリティ対策が十分かを確認します。また、導入後のサポート体制や法改正時のアップデート対応も選定時の大きなポイントです。
5.コストと拡張性のバランス
初期費用や月額料金だけでなく、将来的なユーザー数増加や業務拡大にも柔軟に対応できる拡張性があるかも重要です。料金体系の透明性や、追加コストの有無も比較検討し、長期的なROIを意識して選びましょう。
ビジネスの進化において、会計システムのリプレイスは決して軽視できない重要な決断です。そこで下記の資料では、経理・財務部門と情報システム部門の方たちに向けて、リプレイス時に組織全体を見直す戦略的アプローチを提案しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
請求書支払業務の自動化による導入効果
以下では、請求書支払業務の自動化による導入効果をまとめます。
| 導入効果 | 内容 |
|---|---|
| 業務効率化・時間削減 | 請求書処理の自動化により、手作業や転記作業が大幅に減少。スタッフの作業時間が約70%も削減できた事例もあり、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。 |
| ヒューマンエラー・ミスの削減 | AI-OCRやワークフロー自動化で入力ミスや確認漏れを防止。データ精度が向上し、誤払いや二重支払いのリスクも低減するでしょう。 |
| コンプライアンス・法令対応強化 | システムで承認や証憑保存、履歴管理を自動化することで、規程遵守や電子帳簿保存法・インボイス制度などの法改正にも柔軟に対応できます。 |
| 支払遅延・コスト削減 | 承認・支払プロセスが迅速化し、サプライヤーへの支払遅延が67%減少。紙・郵送・保管コストも削減されます。 |
| 情報の可視化・経営判断の迅速化 | 支出データがリアルタイムで可視化され、経営層や財務部門が迅速かつ正確に意思決定できる基盤となります。 |
| IT・管理負担の軽減 | クラウド型システム導入により、ITスタッフの運用・保守負担が削減されます。システム管理もシンプルになるのがメリットです。 |
このように請求書支払業務の自動化は、効率化・コスト削減・リスク低減・ガバナンス強化など多面的な効果をもたらします。
下記の資料では、累計11,000社以上が導入し、高度な技術力で快適な操作性を提供している経営基盤ソリューション(財務会計|人事給与)SuperStream-NXの製品資料を無料でダウンロードできます。ぜひご参照ください。
請求書管理の効率化はキヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」におまかせ!
キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」は、AI-OCRによる請求書データの自動読取や仕訳・支払伝票の自動作成、会計システムとのシームレスな連携により、請求書管理業務の大幅な効率化を実現します。
インボイス制度や電子帳簿保存法にも標準対応し、Peppolネットワークを活用したデジタルインボイスの発行・受領・証憑保存も可能です。
クラウド型で保守・アップデートも自動化され、法改正や監査にも柔軟に対応。11,000社以上の導入実績が信頼の証です。
下記のページでは、「経営基盤ソリューション SuperStream-NX」の詳しい内容を解説しています。登録不要でご覧いただけますので、この機会にぜひご参照ください。
請求書管理の効率化を実現したいとお考えの方は、オンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
著者プロフィール
スーパーストリーム 商品企画担当
1970年6月生まれ、宮城県生まれ、横浜育ち。
旧公認会計士第二次試験合格後、監査法人にて国内企業の監査業務に携わる。
その後、米国系ERPパッケージベンダーにて、営業支援、製品ローカライズ、パッケージ導入業務に従事する。2003年4月より現職。SuperStream会計製品の商品企画を担当する。