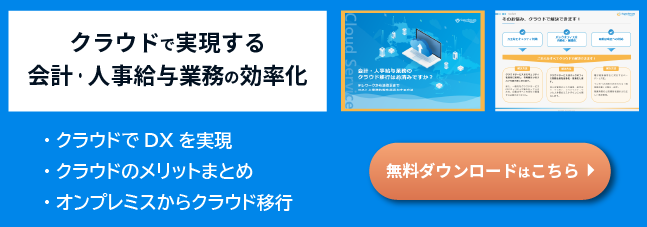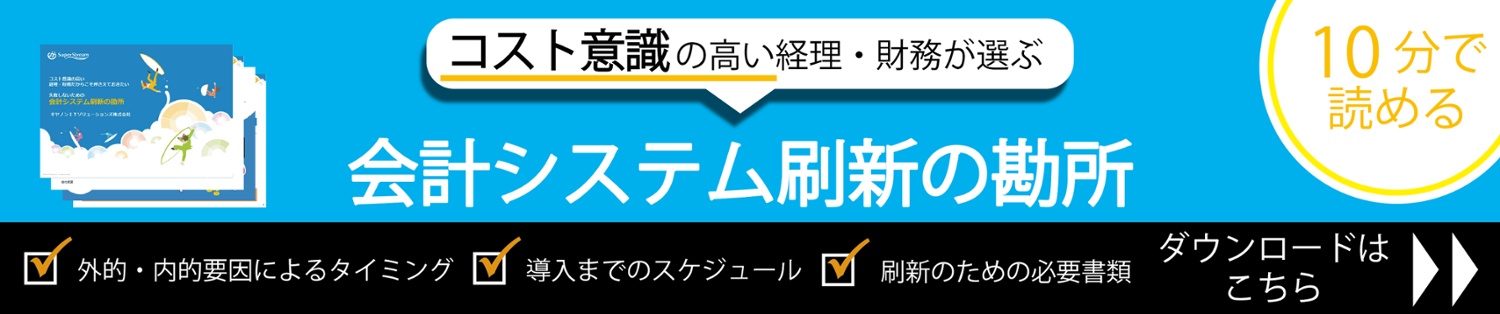公認会計士 中田清穂氏執筆|会計ソフトのリプレイスの目的と留意点トレンド情報
公認会計士 中田清穂氏執筆|会計ソフトのリプレイスの目的と留意点トレンド情報
公開日:2023年11月22日
「会計ソフトの移行を検討しているのですが、何に気をつければ良いですか?」といったご質問をよくいただきます。
システムの移行は、「乗り換え」や「入れ替え」などと言うこともありますが、「リプレイス」とか「リプレース」などと言われることもあります。
システムリプレイスには様々なシステムのものがありますが、会計ソフトのリプレイスには特徴があります。
以下のような特徴を持つ会計ソフトのリプレイスについて、本コラムでは、どのような目的で検討されることが多いのか、留意すべきリプレイスの際のポイントは何か、について解説したいと思います。
目次
会計ソフトの特徴
-
製品によってカバーする機能の領域が異なる
購買管理や販売管理のシステムであれば、購買や販売に限定したシステムになりますが、会計ソフトの場合、日常経理業務としての仕訳入力や決算書の作成といった主要業務のほか、入金や支払といった財務関連の業務や経営意思決定のための予算管理や部門別管理などもあり、開発されたシステムによってそのカバー領域は異なります。
-
会計ソフトはデータの流れの最下流
また、会計ソフトは、社内の情報の流れの中では、「最下流」で情報を受け止めるシステムなので、上流に位置する各システムとデータ連携をすることも特徴となります。
-
紙を扱うことが多い
さらに、会計ソフトを利用する経理業務は、請求書、領収書あるいは伝票などといった『紙』を扱う業務が多いことも特徴です。
会計ソフトをリプレイスする目的
会計ソフトのリプレイスを検討する目的には、以下のようなものがあります。
-
ソフトウェアの保守の終了
自社でこれまでに使っていたソフトウェアの開発元が、事業撤退や新しいバージョンの製品にシフトするなど、自社で使っていたソフトウェアに関する保守が終わってしまうことがあります。
自社では問題なく使っているのに、開発元の都合で使えなくなるのです。 -
ハードウエアの刷新
使っていたPCやサーバーを刷新することで、処理速度やデータ保存量を大幅に改善することができます。
しかし、新しいハードウエアでは、自社でこれまでに使ってきたソフトウェアの動作保証がされていないことがあります。 -
クラウドへの移行
会計ソフトがクラウドサービスの場合、以下のようなメリットがあるので、いわゆるオンプレミス型をやめてクラウド型に変える動きが活発になっています。
-
専用のPCやサーバーが必要なく、システム部門の負担を軽減する
-
出社しなくても作業ができ、在宅勤務を促進する
-
同時に複数人で作業ができる
-
バージョンアップやアップデートの更新作業が要らないので手間や費用がかからず、効率化やコスト削減に効果がある
-
カード会社や金融機関などと連携すれば、入力や仕訳の作業の正確性向上や効率化に効果がある
-
-
法制度への対応
税制や会計基準の変更などがあった場合、ソフトウェアの開発元がタイムリーに対応しなければ、自社の経理・決算業務を適切に行うことができなくなります。
度重なる制度変更に対して、これまでにタイムリーに対応してこなかった開発元を信頼することはできません。
今後も、インボイス制度や電子帳簿保存法、さらにはリース会計基準などが改正される可能性があります。
今お使いの会計ソフトが、信頼できない開発元によって提供されている場合には、他の会計ソフトの情報を早めに集めておくことは有用だと思います。
特に、「紙」を主体とした経理業務を変革するためにリプレイスする場合には、ペーパレス機能や他のシステムとデータ連携しやすい設計思想で開発された会計ソフトにリプレイスすることも、最近では多くなってきています。 -
企業規模の拡大・成長
事業が拡大してくると、社員の数、部門の数、製造拠点の数、販路の数、取り扱い製品の数、など、様々な「切り口」の数が増加し、それぞれの「切り口」が複雑に絡み始めます。
そうなると、当初問題なく利用できていた会計ソフトも、企業規模の拡大とともに、様々な課題を抱えるようになってきます。
特に、新規上場や新規公開などの、いわゆるIPOを控えるようになると、IPOのために必須となる、会計監査や内部統制などに耐えうる会計ソフトを利用していないと、監査法人から相手にされない、「監査難民」になることさえあり得ます。
会計ソフトをリプレイスする場合の留意点
-
既存システムからのデータ移行
経理業務は、前年同期比など、残高や取引高を過去のデータと比較することが非常に多いのが特徴です。
したがって、それまで使っていたシステムの過去のデータを移行して、新しい会計ソフトでも比較できるようにしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、新旧の異なるシステム間で、データの形式をあわせなければならないことが当然のように発生することです。
新しく利用することになった会計ソフトには、「部門」や「外貨対応」がないなど、過去のデータの一部が移行できなくなることもあるので、リプレイスする会計ソフトの機能については、検討段階での十分な調査が必要です。
つまり、新しい会計ソフトを導入する前に、異なるシステム間でのデータの互換性を確認することがとても重要なのです。
さらに、どのような移行作業が発生するのかを確認することも、導入期間や誰にどのくらいの負荷がかかるかを把握しておくためにも重要です。ここを疎かにすると、導入スケジュールがどんどん遅延したり、導入にあたった社員の健康被害も発生します。 -
サポートデスクの充実度
また、新しく購入する会計ソフトのサポートデスクなどの充実度も調べておくと安心です。
いくら便利そうだと感じても、ずっと使い続けるものですから、サポートデスクがひどいと、経理・決算業務に支障をきたす可能性があります。
導入時には、追加料金はかかるものの、データ移行を支援するサービスを提供する開発元やその販売パートナー企業もあるため、各社の支援プランを確認することも有用です。 -
新旧システムの並行運用
並行運用とは、それまで使っていたシステムと新しく利用することにしたシステムを同時に使うことです。
旧システムからいきなり新システムへ移行するのは大きなリスクがあります。
新システムを使い始めて、すぐに使えないとか業務効率が著しく悪化するなど、想定外のことが起きる場合があります。
したがって、新システムのテストをしながら数カ月間は、旧システムを使い続ける、並行運用をするのが安全でしょう。
無駄な業務をするイメージもあるため、並行運用をしないで、いきなり新システムに移行するケースもありますが、前述の通り、リスクは高いのでお勧めできません。 -
本番前の研修
経理業務は、毎日の日常業務をこなす必要があり、支払や入金業務など、間違いがあってはならない業務です。
したがって、本番稼働前に、システム連携の手続きや利用する機能の確認など、実際に利用する社員が研修を受けることが大切です。
また機能の範囲が広い会計ソフトを利用する場合には、経費精算やワークフローシステムの機能などを使うケースもあるため、現場部門の業務にも影響があり、現場部門にも丁寧に説明会を開いて、社内の質問窓口を用意しておくことも有用です。
著者プロフィール
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。