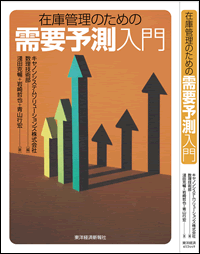SDGsとSCM ~世界的に注目の高まるSDGsとSCMの関わり~コラム
公開日:2021年4月1日

昨今、経済・社会環境は急激に変化し続けています。それによっておこる社会課題やトレンドに対し、需要予測・需給計画は柔軟に対応していく必要があります。
そこで本コラムでは、需要予測・需給業務の担当者や最新のトレンドを学びたい方向けに、今後必要とされる需要予測・需給計画の取り組みやポイントについて、弊社コンサルタント独自の視点で解説します。
SDGsとSCM
SDGs(エス・ディー・ジーズ)は、Sustainable Development Goalsの略で持続的な開発目標を意味します。SDGsは、約200ヵ国の政府関係者、NGOなどの市民代表、研究者などが3年をかけて、「今の世界の課題は何か」を議論し、その課題解決を2030年までの目標として17のゴールと169のターゲット(具体的な目標)にまとめ、2015年に発表されました。SDGsの発表をうけ、日本政府や多くの民間企業で、SDGsの達成にむけて様々な取り組みがなされています。たとえば、2020年7月よりはじまった「レジ袋有料化」は記憶に新しいところです。レジ袋の有料化は、SDGsにおけるゴール14「海の豊かさを守ろう」およびターゲット14.1「2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。」にそった施策といえます。
今回のコラムでは、SDGsが企業活動であるサプライチェーンマネジメントと、どのように関わってくるのか、考察します。
調達先の労働環境
日本人にとって、貧困や児童労働は、日常からかけはなれた課題かもしれませんが、海外の調達先の従業員はどうでしょうか?ILO(国際労働機関)によると、2016年時点、世界の子供の10人1人、約1億5,200万人が児童労働しているそうです。昨今、「商品はどこで、誰によってつくられたのか」「極端な低賃金で働かされていないか」とサプライチェーンの川上の実態を明らかにし、川下に位置するメーカーも責任を負うべきという機運が高まっており、調達先の従業員がおかれた状況を把握していなかったことで、企業イメージをダウンさせることになりかねません。
調達先の労働者の賃金や労働環境について目を向けることは、SDGsにおける、ゴール1「貧困をなくそう」およびターゲット1.1「2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる」や、ひいては、子供が学校に通えるようになれば、ゴール4「質の高い教育をみんなに」にむけて貢献できることになります。

生産・物流の高度化
従来のサプライチェーンマネジメントでは、「在庫は悪」と考え、需要にあわせて生産・物流の能力を増減させてきました。しかし、生産現場では需要が増える時期に、従業員を増やす、もしくは長時間労働を続けてもらうような勤務体制で、従業員に負担をかけながら臨むことになります。
また、物流現場では、近年、ネット販売の増加やトラックドライバー不足から、需要が増える時期に、トラックそのものを調達することが難しくなっています。対応として、生産現場にロボットを導入して、従業員を肉体労働から高付加価値でやりがいのある業務に配置転換する、需要が増加する前に、前倒しで生産や輸送を計画/実行するという取り組みを行う企業が増えています。また、生産、物流の計画自体も複雑度が増すため、人間が計画するのではなく、最新のAI技術を応用して計画を立案するケースもあります。
このように生産・物流の高度化に取り組むことは、SDGsにおけるゴール8「働きがいも経済成長も」およびゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」に貢献することになります。
食品ロスの低減
発展途上国の経済発展により、世界の人口は増加の一途をたどっており、将来、食糧生産が、追いつかなることが懸念されています。対応として、食料増産の技術開発に取り組む一方で、食品廃棄を減らすことも重要と考えられています。国よる調査では、2017年度国内で、まだ食べられる食料612万トンが廃棄されたとあり、世界全体の食糧援助量390万トンを上回ります。環境省は、食品ロスの削減に役立つ情報を提供する「食品ロスポータルサイト」を立ち上げており、企業での取り組み事例として、気象情報を活用した需要予測の精度向上が紹介されています。
食品ロスの解消に向けた取り組みを行うことは、SDGsにおける、ゴール12「つくる責任 つかう責任」およびターゲット12.3「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる」の達成に貢献することになります。
おわりに
2020年4月、教育指導要領が改訂され、小学校の教科書にもSDGsについて記載されるようになりました。また、ほぼすべての中高一貫校で、授業や課外カリキュラムにSDGsが採り入られており、これからの消費を支える若者は、「良いものを安く」という経済合理性だけでなく、「SDGsの達成に貢献できるか」といった観点で商品、ブランドを選択するようになると予想されています。企業は、サプライチェーンマネジメントの側面からも、SDGsの達成に貢献し、消費者にアピールすることの重要性が高まっているのではないでしょうか。
筆者紹介

武田 勝徳(たけだ かつのり) R&D本部 数理技術部 シニアコンサルティングスペシャリスト
博士(工学)。
需要予測・需給計画ソリューション FOREMAST(フォーマスト)のシステム導入プロジェクトに従事。
趣味はキャンプ。キャンプ沼にハマり、道具に散財中。
関連書籍など
在庫管理のための需要予測入門
FOREMAST担当コンサルタントが執筆した需要予測入門書です。
どのような需要予測システムを導入すればよいかお悩みの方のために、実務に精通したコンサルタントが基本知識からシステム導入時に考慮すべきポイントまでをやさしく解説しています。
在庫管理のための需要予測入門
キヤノンシステムソリューションズ株式会社数理技術部[編]
淺田 克暢+岩崎 哲也+青山 行宏[著]
- 出版社:東洋経済新報社
- 発売日:2004年12月22日
- ISBN:4492531874
- 価格(税込):1,980円
関連するソリューション・製品
- FOREMAST
- 大量の在庫を抱えているのに欠品や納期遅れが発生していませんか?「キャッシュフロー経営」が叫ばれる中、多くの企業で在庫削減が重要な経営課題となってきています。しかし一方で、お客さまからの即納・短納期要求は益々強くなってきており、欠品の発生が企業経営に大きな影響を与えるケースも増えてきました。FOREMASTは、科学的な需要予測に基づく在庫補充計画と、需給計画・実績情報の共有支援、問題の見える化により、欠品なき在庫削減の実現を支援します。