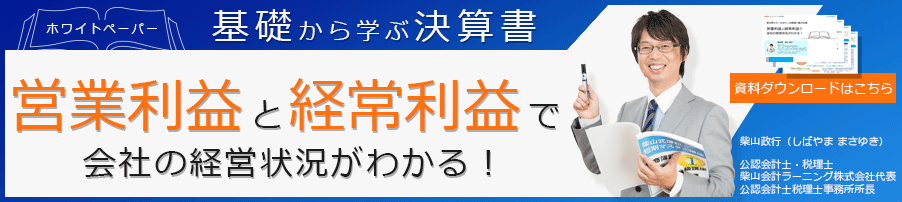よくわかる、使える会計知識 ~円安又は円高・為替レートの変動が企業の業績に与える影響~新しい本社機能に生まれ変わるためステップアップロードマップ
よくわかる、使える会計知識 ~円安又は円高・為替レートの変動が企業の業績に与える影響~新しい本社機能に生まれ変わるためステップアップロードマップ
公開日:2025年11月13日
2024年度は円安基調で上場企業全体の為替差益が1.3兆円
グローバル展開をする企業の決算を読み解くために必要な為替差損益の知識
2025年9月17日から始まる日経朝刊「投資欄」でのシリーズが興味深いものでした。
投資を行うにはとても重要な資料となる企業の財務諸表を読み解く会計知識を解説する「会計フォローアップ」という連載記事です。その第一回のテーマが「為替差損益」でした。
グローバルに事業を展開する日本企業にとって、為替相場の変動は避けて通れないテーマです。とくに自動車や電機といった輸出依存度の高い企業は、ドル円の水準によって収益が大きく動きます。
上場企業は売上高の約6割を海外で稼ぐとも言われています。
海外で稼いだお金は外貨建てとなっており、これらの外国通貨を日本円に換算する際にカギとなるのが為替相場です。
2024年度は円安基調が続いたため、上場企業全体で1.3兆円もの為替差益が計上されました。
たとえば、9月16日の日経電子版では為替差益の計上額が大きな企業の例として、トヨタ自動車の7,052億円、日立製作所の475億円、パナソニックHDの423億円などがあげられており、数百億円~数千億円単位での多額な為替差益が計上されている様子がうかがえます。
円安とは、1ドルを売却し円を購入するために必要な円建ての金額が大きくなることを意味しますね。
たとえば、1ドルを売ると140円が手に入っていたのが、のちに1ドルの売却で150円が手に入るようになると、それは1ドルに対して10円多くの円が必要になるという事なので、円の価値が下がったことになり、これを円安の状態と言います。
反対の見方をすれば、1ドルの価値が円に対して高くなったことを意味するので、ドル高と言い換えることもできます。
一方で、2025年度は円高方向に振れており、状況は一転する可能性があります。
以降では、会社の業務上において、海外取引を行うなど、為替相場の影響を考えて仕事をする人や、株式投資をする際に海外取引を活発に行っている企業への投資を積極的に行っている人などを想定し、為替差損益の仕組みや会計処理、企業業績や投資判断への影響について考察を加えていきます。
為替差損益が発生する2つのタイミング
-
①取引から決済までの間
例えば、1ドル=140円のときに10ドルの商品を輸出したとします。この時点で売上高は1,400円として計上されます。ところが代金を3か月後に回収するとき、もし1ドル=150円になっていれば、受け取れる金額は1,500円。差額の100円が「為替差益」です。逆に130円になっていれば1,300円しか受け取れず、100円の「為替差損」が発生します。
-
②決算時点での外貨換算
もう一つの典型例が、決算時点での外貨建て資産や負債の評価です。たとえば1ドル=150円のときに100ドルを借り入れた場合、負債は15,000円として計上されます。しかし、期末に1ドル=140円に下がっていれば、同じ100ドルの負債は14,000円に評価替えされ、差額の1,000円が為替差益となります。
為替差損益の会計処理と決算書の表示例
会計上の扱い
日本基準では、為替差損益は「営業外損益」に含まれます。つまり、本業のもうけではなく金融的な要因による損益として扱われるわけです。国際会計基準(IFRS)では、金融収益や費用の一部に含めるケースが一般的です。
(参考)簿記会計でよく使われる、為替相場に関する呼び名と略称
- 為替相場の種類
-
-
①直物為替相場(じきものかわせそうば)…SR(Spot Rate)
取引時(または発生時)の為替相場…HR(Historical Rate)
決算時の為替相場…CR(Current Rate)
期中平均為替相場…AR(Average Rate) -
②先物為替相場…FR(Forward Rate)
-
- 外貨表示の原価と時価の呼び方
-
-
①外国通貨による原価…HC(Historical Cost)
-
②外国通貨による時価(または実質価額)…CC(Current Cost)
-
それでは、以下では簡単な取引例をもとに、会計処理の具体例を見てみましょう。
(設例1:取引発生時点の仕訳)
A社は、海外の取引先に向けて、1,000ドルの商品を100個輸出した。取引発生時の為替相場は1ドル140円であった。販売代金は3カ月後に入金する予定である。
| (借) | 売掛金 | 14,000,000 | (貸) | 売上 | 14,000,000 |
-
※
14,000,000円=1,000ドル×100個×@140円
(設例2:決算時の仕訳)
上記の売掛金14,000,000円(1,000ドル×100個@140円)につき、発生時から1カ月経過した決算日時点における為替相場は@144円であった。
売掛金のような貨幣で回収する資産(貨幣性資産ともいう)は、決算日時点における為替相場(決算日レート)で円建て評価をし直すのが現行の会計ルールです。
したがって、決算日レートと取引発生時の為替レートとの差額につき、売掛金の残高を調整し、為替差損益を計上する仕訳を行います。
| (借) | 売掛金 | 400,000 | (貸) | 為替差益 | 400,000 |
-
※
400,000円=1,000ドル×100個×@(144-140)円
この場合の決算書表示は次のようになります。
| 貸借対照表 | 損益計算書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | |||
| 売掛金 | 14,400,000 | 営業外収益 | 400,000 | |||
(設例3:売掛金を決済(回収)した時の仕訳)
上記の売掛金14,400,000円(1,000ドル×100個×@144円)につき、期首から2カ月経過した入金期日に普通預金口座への振り込みがあった。入金時の為替相場は@150円であった。
この場合、売掛金14,400,000円(前期末の決算日レート換算)につき、回収時の円建て金額は1,000ドル×100個×@150円(回収時の為替レート)=15,000,000円となります。
| (借) | 現金預金 | 15,000,000 | (貸) | 売掛金 為替差益 |
14,400,000 600,000 |
-
※
為替差損益(収益)600,000円=15,000,000円-14,400,000円
この場合の決算書表示は次のようになります。
| 貸借対照表 | 損益計算書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 15,000,000 | : | : | |||
| 売掛金 | 0 | 営業外収益 | 600,000 | |||
上の一連の取引から分かることは、輸出時の為替レート@140円から売掛金の回収時における為替レート@150円の差額である為替変動部分@10円に関連して、1,000ドル×100個×@10円=1,000,000円の為替差益(営業外収益)が発生したが、決算日までの為替変動部分400,000円は前期の決算における収益として計上され、決算日の翌日から回収日までの為替変動部分600,000円は当期の収益として配分される、ということになりますね。
以上は、外貨建て売掛金などの資産を保有している際に円安に為替相場が変動した場合を前提としています。これは、為替相場が自社に有利に働いた場合であり、為替差損益が企業の収益として計上された場合を意味します。
反対に、外貨建て売掛金などの資産を保有している際に円高(1ドル140円から135円になるなど)に為替相場が変動した場合は、為替相場が自社に不利に働いた場合であり、為替差損益が企業の費用として計上されることになるのですね。
以上より、投資家として決算書を読む際には、営業上の利益と為替差損益を分けて考えることが大切です。
為替による一時的な変動で黒字や赤字が拡大しているだけなのか、それとも本業の競争力に基づく収益改善なのかを見極める必要もあります。
為替が売上や利益に直接影響する場合
為替差損益とは別に、売上高や仕入原価そのものが為替の影響を受けるケースもあります。
-
輸出企業
1ドル=140円で10ドルの商品を売ると売上は1,400円。翌期に1ドル=150円なら同じ10ドルが1,500円となり、売上高が増えます。円安は輸出企業にとって追い風です。
-
輸入企業
逆に輸入型の企業では、円安はコスト増につながります。140円で仕入れていた10ドルの商品が、150円では1,500円になり、利益を圧迫します。
-
海外子会社の業績換算
日本企業の多くは海外に子会社を持っています。その業績を円換算する際も、一般に期中平均レートを用いることが多いです。円安なら売上・利益が膨らみ、円高なら縮小します。
実際の企業への影響
ある試算によると、対ドルで1円円安が進むと主要企業の経常利益は平均0.3%押し上げられるともいわれています。
2024年度に計上された為替差益は約1兆3,500億円で、その中でもトヨタ自動車が7,052億円を占め、ホンダやソニーグループなども大きなプラス効果を得ています。
ただし、2025年度に入り円高方向に動き出したことで、これまでの「円安メリット」が逆風に転じる可能性が高まっています。
投資判断への生かし方
投資家が為替動向を企業分析にどう取り入れるべきか、いくつかのポイントを挙げます。
-
業績予想の前提レートを確認
決算短信や有価証券報告書には、為替が1円動くと利益がどのくらい変動するかも開示されている場合があります。
-
本業と為替要因を切り分ける
決算書に為替差益が大きく計上されていても、それは必ずしも企業の競争力が高まった結果ではありません。営業利益の推移や国内外の販売動向をあわせて見ることが重要です。
-
為替ヘッジの有無を把握する
先物予約や通貨スワップなどでリスクを抑えている企業もありますが、完全に回避することは困難です。ヘッジ方針や割合を開示しているかもチェックポイントになります。
為替差損益は、一見すると簿記の教科書に載っているシンプルな仕訳に見えます。
しかし実際には、円安・円高の動きが日本企業の決算や投資家の判断に大きな影響を与えています。
2024年度は円安効果で上場企業全体が1.3兆円のプラスを得ましたが、2025年度は円高が進む中で逆にマイナスに働く恐れがあります。投資家としては、企業が設定する為替前提や感応度を意識し、本業の収益力と為替の一時的な揺れを区別して判断する姿勢が欠かせません。
為替相場は経済情勢や金融政策によって日々変動します。簿記や会計の基礎知識を生かしつつ、ニュースや企業開示資料を組み合わせて読み解くことが、賢い投資判断につながるでしょう。
為替リスクを回避するためのヘッジ手段としての為替予約
(1)為替予約とは
企業が将来に外貨と日本円とを交換するときの為替相場を、外国為替の業務を行う銀行との間で、現時点であらかじめ契約しておくことです。
為替予約を行う目的は、外貨建て資産・負債の為替相場変動にともなう損失を軽減・回避することが基本的な目的です。これをリスク・ヘッジ目的とも呼びます。
たとえば、1ドル139円で原材料を海外から仕入れた時、仕入時の為替相場よりも円安になる(たとえば1ドル145円のように、円の交換金額が高くなる)と、支払額が増加するために不利になります。
そのような場合は、円安になったときに為替差益が出るように、たとえば取引銀行との間で将来、一定の額の円を買う為替予約(たとえば1ドル140円で買う約束)をすると、それ以上円安になっても、支払額を140円に限定できるので、リスクの軽減が可能になります。
(2)為替予約の会計処理
原則的な会計処理として、先物取引などと同じ会計処理を行う独立処理というものがありますが、ここでは、実務上事務の簡便化を目的として多く採用される「振当処理」という会計処理について言及したいと思います。
振当処理とは、ヘッジ対象となる外貨建ての売掛金や買掛金などと為替予約の取引を一体に考えて会計処理する方法です。
ここではシンプルな例として、輸出や輸入の取引をする前に、あらかじめ為替予約を銀行と締結していた場合を例にとり、会計処理のやり方を見ていきたいと思います。
(例①)1/1に1,000ドルの買い予約をした。この時の予約レートは@140円である。
-
※
仕訳なし。(特に資産・負債の発生もなく、現金預金のやり取りもないため)
(例②)2/1に商品1,000ドルを仕入れた。支払は4/30、この日の直物レートは@139円である。
| 2/1 | (借) | 仕入 | 140,000 | (貸) | 買掛金 | 140,000 |
-
※
この日の為替相場(直物レート)は@139円ですが、すでに1/1の為替予約で@140円での1,000ドルの購入ができることが決まっており、このドルで買掛金を支払うことがわかっているため、予約レートの@140円で買掛金を計上すればよいことになります。
(例③)3/31(決算日)になった。この日の直物レートは@145円の円安となっていた。
-
※
仕訳なし。
もしも為替予約をしていなければ、買掛金の支払いはその時々の直物レートをもとに金額が決まるため、決算日になったら決算日のレートで買掛金を評価しなおさなければならないですが、今回はすでに為替予約で@140円での買掛金の支払いが決まっているため、期末になって為替レートが変動しても、特に修正の仕訳をする必要がありません。便利ですね!
(例④)4/30に買掛金1,000ドルの支払いを普通預金から行った。この日の直物レートは@147円である。
| 4/30 | (借) | 買掛金 | 140,000 | (貸) | 現金預金 | 140,000 |
-
※
もしも為替予約をしていなければ、この日の直物レートで@147円×1,000ドル=147,000円の支払いをしなければならない所でした。それが140,000円の支払いで済んだのですから、為替予約は外貨建取引をする際に、為替相場が不利に変動した時の多額の為替損失の発生を制限してくれるありがたい存在なのですね。
このように、為替相場の変動リスクへの対処の仕方がいろいろあり、実務の現場では必要に応じて企業は為替予約や通貨オプションなどの防衛手段をとっているのですね。
以上、様々な視点から為替差損益についてみてきました。
今後、ますますグローバル化が進む企業活動において、外国為替の問題と為替相場の変動による損失発生のリスクを抑えるなど、企業努力を為替差損益などの会計情報でチェックすることの重要性が少しでもイメージできたら幸いです。
著者プロフィール
柴山政行(しばやま まさゆき)
公認会計士・税理士
柴山会計ラーニング株式会社代表 公認会計士税理士事務所所長
公認会計士・税理士としての業務のほか、経営者や税理士向けにコンサルティング指導、メルマガ・インターネットを中心とした簿記・会計教材の製作、会計関連の講演やセミナーなど、多岐にわたって精力的に行っている。また、小中学生から始められる簿記・会計教育「キッズ★BOKI」のメソッドを開発し、その普及に力を注いでいる。