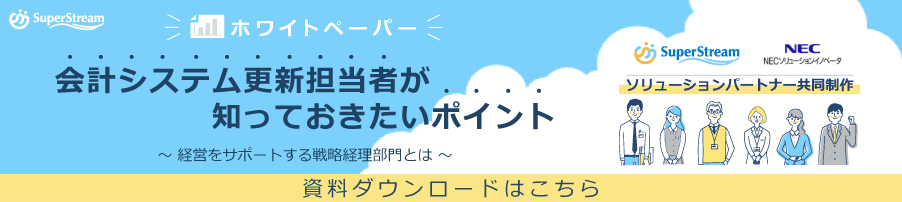新リース会計基準対応を生成AIで乗り切る:第2回 生成AIに「リースの期間」について聞いてみよう!公認会計士 中田清穂のインボイス制度と電子帳簿保存法の解説講座
新リース会計基準対応を生成AIで乗り切る:第2回 生成AIに「リースの期間」について聞いてみよう!公認会計士 中田清穂のインボイス制度と電子帳簿保存法の解説講座
公開日:2025年11月13日
今回は、「リースの期間」について、生成AI(Copilot)に聞いてみます。
中田:新リース会計基準における「リースの期間」について説明してください。
Copilot:新リース会計基準(企業会計基準第34号および適用指針第33号)における「リース期間」の定義は、従来の基準よりも実態に即した判断が求められるようになっています。
これはIFRS第16号「リース」と整合性を図る形で設計されており、以下のような構成要素を含みます。
- リース期間の定義と構成要素
- 新リース会計基準では、以下の期間を総合的に判断して「リース期間」を決定します:
- 契約上、解約できない期間
-
- 契約書に明記された、借手が資産を使用できる期間で、途中解約ができない期間。
- 延長オプションの対象期間
-
- 借手が延長オプションを「合理的に確実に行使する」と判断される場合、その延長期間も含める。
- 判断には、経済的インセンティブ(例:再契約コストの高さ、代替資産の入手困難性など)を考慮。
- 解約オプションの対象期間
-
- 借手が解約オプションを「合理的に確実に行使しない」と判断される場合、その期間も含める。
- 解約に伴うペナルティや実務上の困難さがある場合、解約オプションがあっても含める可能性が高い。
- 実務上の検討ポイント
-
- 契約書の精査:延長・解約オプションの有無と条件を確認。
- 合理的に確実な判断:過去の契約履歴、経済的要因、業務上の必要性などを総合的に評価。
- グルーピングと文書化:類型別に契約を整理し、判断根拠を記録することが推奨されます。
- 影響と留意点
-
- リース期間が長くなると、使用権資産およびリース負債の計上額が増加し、財務諸表への影響が大きくなります。
- 延長オプションや自動更新条項の扱いは、契約の実態に即して慎重に判断する必要があります。
こんな回答内容では、新リース会計基準において、とても重要で会計基準の中心概念である「リース期間」についての理解を深めるには役立ちませんね。
そこで、追加の質問をしてみます。
中田:ありがとうございます。
しかし、延長オプションや解約オプションを、リース期間に含めるかどうかの判断については、「経済的インセンティブを考慮する」と説明されています。
この「経済的インセンティブ」をもっとわかりやすく教えてください。
Copilot:もちろんです、清穂さん。
新リース会計基準(企業会計基準第34号)やIFRS第16号では、延長オプションや解約オプションをリース期間に含めるかどうかの判断において「経済的インセンティブ(economic incentive)」の有無が重要な鍵となります。これは単なる契約条項の有無ではなく、借手が実際に延長や解約を選択する可能性に影響を与える「経済的な理由や動機」を指します。
- 経済的インセンティブとは?
- 借手が延長オプションを行使する、または解約オプションを行使しない「合理的に確実」と判断される背景にある、経済的な利得・不利のことです。以下のような要因が該当します:
- 延長オプションを行使するインセンティブ
-
-
代替資産の入手が困難または高コスト
例:特殊な機械で、同等品の調達に時間や費用がかかる。
-
立地や設備が業務に不可欠
例:店舗が好立地にあり、移転すると売上が減少する可能性が高い。
-
初期投資の回収が延長期間に依存
例:内装工事費を償却するには延長期間が必要。
-
契約条件が有利
例:延長期間の賃料が市場価格より安い。
-
代替資産の入手が困難または高コスト
- 解約オプションを行使しないインセンティブ
-
-
解約に伴うペナルティが大きい
例:違約金や残存リース料の支払い義務。
-
業務上の中断リスク
例:解約すると業務が止まり、損失が発生する。
-
代替手段が非効率
例:他の施設では業務が成立しない、訓練や移行コストが高い。
-
解約に伴うペナルティが大きい
- 実務上の判断方法
-
- 契約書だけでなく、業務実態を確認する
- 過去の延長・解約履歴を分析する
- 社内の意思決定プロセス(稟議書など)を参照する
- 経済的要因を定量的に評価する(例:NPV分析)
- IFRS第16号の参考パラグラフ
-
- IFRS 16.19:「借手は、延長オプションを行使することが合理的に確実である場合には、その延長期間をリース期間に含める」
- IFRS 16.B37:「合理的に確実であるかどうかの判断には、経済的インセンティブを含むすべての関連事実と状況を考慮する」
「経済的インセンティブ」という用語がかなりわかりやすくなってきましたね。
内容的にも間違っていないようです。
しかし、「経済的インセンティブ」というのは、単なる「インセンティブ」と違うはずです。
ここについて聞いてみましょう。
中田:ありがとうございます。
しかし、単なる「インセンティブ」ではなく、「経済的インセンティブ」という表現にしているのはなぜですか。
経営的に使い続ける意図があるから、延長オプションを行使することが確実ということと違いがありますか?
Copilot:とても鋭いご質問です、清穂さん。
「インセンティブ」ではなく「経済的インセンティブ」という表現が用いられているのは、単なる経営者の意向や戦略的な希望とは異なり、客観的かつ合理的に裏付けられた経済的要因に基づいて判断すべきことを強調するためです。
- 「経営的意図」と「経済的インセンティブ」の違い
-
観点 経営的意図 経済的インセンティブ 性質 主観的・戦略的 客観的・合理的 判断根拠 経営者の希望や方針 契約条件、市場価格、代替コストなど 監査対応 説明責任が弱い 客観的根拠が求められる リース期間への影響 判断に含めるには慎重 判断に含める可能性が高い - 具体例で比較
-
-
経営的意図のみ
「この店舗は気に入っているから、延長するつもりだ」
これは経営者の希望であり、経済的インセンティブがあるとは限りません。例えば、延長後の賃料が市場より高ければ、希望があっても合理性に欠けます。
-
経済的インセンティブがある場合
「延長期間の賃料は市場価格より30%安く、移転には1,000万円の改装費がかかる」
このような場合、延長オプションを行使することが合理的に確実と判断され、リース期間に含める根拠となります。
-
- IFRS第16号の意図
-
IFRS第16号(および企業会計基準第34号)は、リース期間の判断において「借手の主観的な意図」ではなく、「経済的な合理性」を重視しています。これは財務諸表の信頼性と比較可能性を高めるためです。
IFRS 16.B37では、以下のように明記されています:
An entity shall consider all relevant facts and circumstances that create an economic incentive for the lessee to exercise an option…
引用元 IFRS第16号(および企業会計基準第34号) つまり、「経済的インセンティブ」があるかどうかが、延長や解約オプションの判断において中心的な基準となるのです。
これはかなり正確です。
日本の適用指針にも記載がある内容を、わかりやすく表現して説明していると感じます。
最近のセミナーで、以下のような質問を受けることが多くあります。
自社の中長期計画では、本社移転を想定していないので、自動更新をすることが前提となっています。
この場合、延長オプションとしてどれくらいの期間を契約期間に加えればよいでしょうか。
延長オプションを考慮する際には、延長することが「合理的に確実」であることが説明できなければなりません。
その際、中長期計画は「経営的インセンティブ」であって「経済的インセンティブ」ではありません。
経営者の意図(事業計画など)などといった「主観的な要因」ではなく、延長することが、客観的かつ合理的に裏付けられた経済的要因によって説明されなければならないのです。
したがって、例えば本社として借りている物件が、契約期間が満了した後、
-
新規の賃料が現行の賃料よりも大きく下げられる
-
現在の物件に対して、大規模改良をしているため、新しい物件に引っ越した場合に、同様の大規模改良が必要となる
-
現在の物件を返却する際には、あまり多額の原状回復コストが発生しない
-
現在借りている物件でなければ、本社機能が果たせないほどの、かけがえのない物件である
-
新規の賃料が、近隣相場と比較して明らかに低くなる
といった状況であれば、客観的かつ合理的に考えて、延長することに経済合理性があると説明できるでしょう。
著者プロフィール
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。