ケーススタディー:教育サービス企業の例データマネジメントサービス
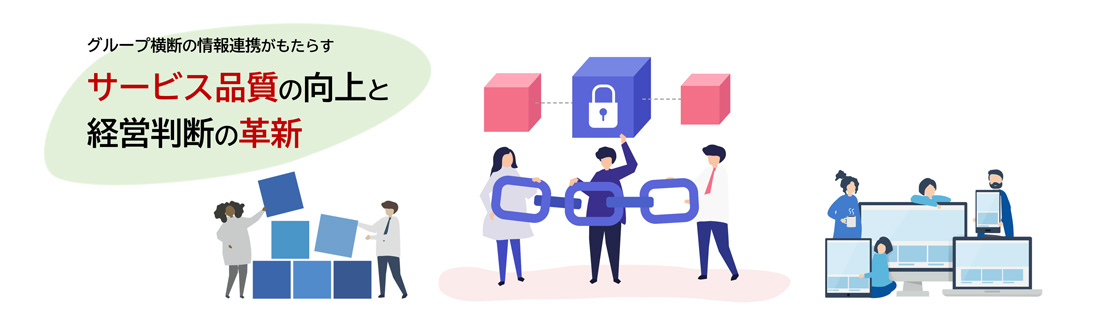

分散していた顧客データの統合に着手した背景についてご紹介いたします。
重複した顧客データの整理と照合を通じて、より良いサービス体制を目指す一環としてご覧ください。
持続的な成長を支えるために、今、必要な一歩
背景・経緯
子どもから高校生まで幅広い年齢層を対象とした教育サービスを提供するB社は、少子化の進行や首都圏における受験の早期化、教育費の増加、業界再編といった環境の変化に直面しています。その中で、生徒一人ひとりに合わせた、より質の高い学びがこれまで以上に重視されるようになりました。
見えてきた問題点は、顧客情報の統合が困難であること
学習支援を中心とした複数のグループ会社を展開するB社は、大きな環境の変化にさらされています。少子化により生徒数が減少する中、保護者や生徒から選ばれる存在となるためには、独自の教育方法やサービスを提供することで、他社との差別化を図ることが重要です。このような外部環境の変化に対して、競合との差別化が必要不可欠な状況にありました。
一方、内部的には、教育の質の向上・維持による高い合格実績を実現することがB社全体の大きな目標として掲げられていました。しかしながら、浮かび上がった問題として、グループ各社それぞれで顧客情報が管理されており、グループを横断した顧客情報の管理と横断情報から得られる相乗効果が発揮できないことでした。
複数のグループ各社を横断した相乗効果が得られにくい状態
B社は複数のグループ会社で構成されており、それぞれが特色ある教育サービスを展開しています。しかし、各社が独自に顧客情報を管理・運用していたため、グループ全体での連携や戦略的な取り組みにおいて、十分な相乗効果が得られにくい状況にありました。
あるグループで成果を上げた施策や運用ノウハウを、他グループへ展開しようとした際にも、顧客情報の管理・運用方法がグループごとに異なるため、情報の横断的な比較や活用が難しく、知見の共有が円滑に進まないという課題がありました。
例えば、生徒への指導内容やカリキュラムの工夫など、各グループで得られた成果が十分に共有されず、グループ間での連携や相乗効果が生まれにくい状況がありました。
こうした状況では、グループ全体での意思決定や施策の検討において、部分最適な視点にとどまり、組織全体の成長を促す仕組みづくりが思うように進みません。
そこで、グループ間の顧客情報を連携する基盤づくりを通じて、学習の質、顧客へのニーズに合った教育サービスの提供を目指す第一歩を踏み出しました。
抱えていた問題事象
- 少子化の進行により、生徒数の維持が難しくなっている
- グループ横断の顧客情報の管理と、横断した情報から得られる相乗効果が発揮できないこと
教育現場の支援の向上を目指して
断片的だった顧客情報から、組織的な連携へ
きめ細やかな教育サービスの提供
こうした問題を踏まえ、B社は「グループ横断で活用できる顧客情報の統合基盤」を構築して、グループ各社や教室の枠を越え、顧客情報を一元的に整理・統合する仕組みを整えることで、教育支援の質を高める土台を作り、よりきめ細やかな教育支援の実現を目指しています。
具体的には、生徒によっては兄弟姉妹が別のグループの教室に通っていたり、家族構成が変化したりと、時間の経過や生活環境の変化に伴って、情報が分散・断片化している状況が見受けられました。
その結果、同じ家族であっても別々の人物として扱われてしまうなど、関連する情報が一つにまとまっておらず、丁寧な教育支援において支障となる場面がありました。
こうした状況を解消し、グループをまたいだ一貫した教育支援を実現していくため、B社では情報を繋ぎ合わせて整理する仕組みの導入を検討することにしました。
これにより、指導の引継ぎや保護者との信頼関係構築がよりスムーズになるとともに、企業全体として教育サービスの質を高めていくことが期待されています。
データ統合に向けた取り組み
情報の照合と整理
名寄せ(なよせ)と、その後のメンテナンス
はじめに着手したことは、生徒のデータの照合と整理です。いわゆる「名寄せ(なよせ)」という作業にあたります。同じ生徒が複数の教室に通っていたり、兄弟姉妹で別の教室に在籍していたりする場合、同一人物であっても、別々に登録されていることがありました。さらに、グループごとにシステムが異なるため、同じ生徒でも違う情報として扱われていることもあり、これらを照合して整理するために「この情報は同一人物」という判断をするための作業は非常に手間と注意を要するものでした。
照合・整理をされたデータが、意味を持って整理された状態になったとき、「情報」として使える状態になります。
ここで重要なことは、データの取り扱いにおいて時間軸を考慮することです。過去のデータや更新されたデータに関して、メンテナンスをしていく必要があります。具体的には、時間の経過とともに、生徒の年齢の変化や取り巻く環境変化、家族構成の変化といったことに応じてサービスの利用状況が日々変わっていきます。これらを考慮したうえで、差分データを毎日チェックし、名寄せ(なよせ)ができていなかったものに対してメンテナンスを行います。名寄せ(なよせ)が誤っている可能性のあるデータを不安要素としてリスト化し、管理をする仕組みを作り、運用していくことで、継続的にデータをメンテナンスしています。
データ統合
グループ各社ごとにバラバラだったシステムの統合
こうしてデータが正しく整理・維持されるようになったことで、グループ各社ごとにバラバラだったシステムの統合にも取り組むことができました。これまでグループ各社で異なるシステムにより管理されていた顧客情報を、現在は一つのクラウド上にまとめて集約しています。分散していた情報を一つにまとめ、兄弟姉妹や家族構成の繋がりも整理することで、グループをまたいでいても一貫したサービス提供ができる体制が整いました。情報が集約されたことで、現場での確認や共有もスムーズになり、対応の質の向上や業務効率化にも繋がっています。このように、「バラバラに存在していた情報」を名寄せ(なよせ)・統合することで、ようやく企業横断的な施策の展開が検討できるようになっていきました。
データをさらに価値あるものとして活用していくためには、データをどのように「蓄積・整理・活用」するかという視点が欠かせません。その設計を支えているものが、データレイク、データウェアハウス、データマートという仕組みになります。
-
データレイク
あらゆる種類の大量データ(例 テキスト、画像、動画など)を保管し、あとで自由に分析や処理ができるようにします。
-
データウェアハウス
異なる情報源から集めたデータをきれいに整形し、統合して保存しておきます。
-
データマート
特定の目的や用途に応じて、必要なデータだけを抽出・加工して格納しておきます。

本格運用に向けた期待と、次のステップ
教育の未来を支える
生徒の生涯に寄り添う教育サービスのパートナー
デジタル基盤の構築が進み、統合されたデータに基づいて迅速かつ的確な意思決定が可能な体制が整いつつあります。これにより、企業全体の経営判断の精度とスピードの両立が期待されます。
経営層と現場では、それぞれの立場で注目する指標や必要となる情報が異なりますが、役割に応じた視点で必要な情報が信頼性の高い形で整理され、可視化される仕組みも徐々に整備されてきています。
また、グループを横断した施策を検討するための土台ができたことで、相乗効果を活かしたサービス展開や、生徒の個性を活かした個別施策の戦略策定など、企業の全体的な成長を促進できるようになることでしょう。
サービスの質の向上という観点では、グループ間での継続的なサービスの利用や途中離脱の防止といった視点から、顧客との長期的な関係構築に向けた施策についても、より具体的な検討が可能となる環境が整いつつあります。
このプロジェクトは始まったばかりであり、今後さらに進化していく段階にあります。統合されたデータを活用しながら、プロセスの改善や施策の拡充を重ねることで、目指す姿の実現に向けた一歩一歩が着実に進んでいくことを目指しています。
将来的には、データ分析に基づいたプロセス改善を通じて、生徒数の増加や、生涯にわたり学び続けるための教育サービスを提供することで、長期的な関係構築をしていくことが理想的です。
生徒一人ひとりの個性に寄り添った質の高い教育サービスを提供し、未来を担う人材の育成に貢献することで、教育分野における「信頼される揺るぎないパートナー」としての存在を目指しています。
期待している効果
- 経営判断の迅速化
- グループ各社を横断した企業全体の視点による施策の策定
- 生徒数の増加・長期的な顧客との関係構築の土台作り
将来目指したい姿
- 個別指導で個性に合わせた教育サービスの提供を強化
- 差別化した独占ポジションの確立
- 変化の時代を生き抜く人材の可能性を広げていくことに貢献
キヤノンITソリューションズの提供価値
当社の強みと支援領域は、急速に変化する環境下で、お客さま自身では可視化しきれない課題の構造を明らかにし、解決への道筋を共に設計していく力にあります。まだ顕在化していない潜在的な課題に丁寧に向き合い、顧客の企業理念や事業戦略への深い理解をもとにしたヒアリングと提案により、信頼を築いてまいりました。
また、教育領域における知見と経験を背景に、分断されたシステムの統合を推進し、関係者間の合意形成を支援するファシリテーション力、加えてデジタル技術を活用した高い実装力と構築力も当社の強みです。
これらの多角的なアプローチにより、私たちは単なるサービス提供にとどまらず、お客さまが目指す将来像の実現に向けて伴走するパートナーとして選ばれています。
関連する製品・ソリューション・サービス
オンラインセミナーのご案内

多くの企業が、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、自社の経営課題を解決したいと考えています。今や、企業としての理想像に近づくために「DX実現」は欠かせないものとなっています。
さらに、CX(顧客体験価値)をキーワードに、お客さまとの関係を見直し、自社のビジネスモデルを変革し、新たな価値を創出しようとする企業も増えています。ロイヤルカスタマーの育成方法を確立し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指すことは、企業にとって大きなプラスとなります。育成戦略としては、データを基に顧客インサイトを得て、消費者ニーズに柔軟に対応し、CXの向上を目指すことが有効です。
DXを推進する上でも「CX」は重要なポイントです。そこで、本セミナーでは、前半でDX実現と課題解決のためのステップを押さえ、後半では実際のCX基盤構築事例を紹介し、そのポイントを解説します。
- 主催:キヤノンITソリューションズ株式会社
- 形式:オンライン
- 参加費:無料
-
※
2025年3月まで開催していた「LTVの最大化をめざすCX事例 」をリニューアルしたセミナーとなります。一部内容に重複があること、あらかじめご了承ください。
-
※
配信内容の録画、録音、撮影についてはお断りさせていただきます。
-
※
個人及び、同業他社様からのお申し込みは、お断りさせていただく場合がございます。
-
※
内容等は、都合により予告無く変更する場合がございます。