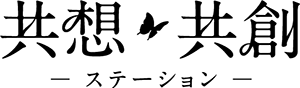 前例がないからこそ挑戦しがいがある!
前例がないからこそ挑戦しがいがある!
データセンターでの直接液冷方式の導入が、新たなビジネスの可能性を広げる
Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み
公開日:2025年8月7日
後列、左から順に、日本ヒューレット・パッカード合同会社 杉田 和之様、松島 隆修様、キヤノンITソリューションズ株式会社 八木 淳寿、青木 陸、南里 恭平
(以下、本文は敬称略)

昨今、生成AIやデータ解析のために高性能なGPUサーバー・HPCサーバーの需要が高まっています。これらのサーバーは高い処理能力を発揮する一方で、膨大な電力を必要とし、発熱量も大幅に増大するため、従来の空冷方式のみで冷却する設置環境では、十分に冷却しきれないという課題が生じています。そこでキヤノンITソリューションズ株式会社(以下、キヤノンITS)は、水冷方式のパイオニアである日本ヒューレット・パッカード合同会社(以下、HPE)と連携し、お客さまの要望に応えるべく、近年注目されている直接液冷方式(以下、DLC:Direct Liquid Cooling)のサーバー設置環境を西東京データセンターにいち早く構築しました。今回は、HPEのメイン担当であったお三方をお招きし、キヤノンITSの担当者4名と共に、日本での先駆的な取り組みとなった本案件について語り合いました。
前例のないことへの挑戦で築いた「DLC」対応のデータセンター
米国ヒューレット・パッカード社とキヤノングループは、古くからパートナーシップを築き、多くの協業により共に発展してきたという歴史があります。今回は、HPEとキヤノンITSがタッグを組み、キヤノンITSが運営する西東京データセンターに、日本のデータセンター事業者内でも、まだあまり実現できていない液冷サーバーを設置可能な高負荷対応サービスを構築しました。
社会インフラの役割を担うデータセンターに求められる電力需要や発熱量が飛躍的に増加し続けていますが、こうした緊急性の高い社会課題に対し、HPEとキヤノンITSが共に、前例のない挑戦に取り組み、互いに協力しながらゴールを目指しました。本日は、この取り組みについてお話をうかがっていきたいと思います。
はじめに、HPEにおけるDLCへの取り組みについて、お話しいただけますか。
HPE 皆川:今回はこのような機会をいただきありがとうございます。HPEは、エンタープライズ向けのサーバー、ストレージネットワークの販売、サポートなどを主な事業としています。私たちはその中のHPC&AI事業統括本部に属しており、部署名の通りHPC、いわゆるスーパーコンピューターとAIの分野について公共から民間まで幅広く担当しています。
じつは、私たちはもう50年近く液冷方式のサーバーを取り扱っています。海外では早い時期から液冷方式が採用されてきましたが、日本国内でも近年需要が増えてきており、公共系の大学や研究所などの大規模なHPCに関しては、おそらくすでに8割程度が液冷方式になっています。生成AIの急速な進化もありGPU/CPU(中央演算処理装置)の消費電力は大幅な増加傾向にあるため、今後はエンタープライズも含めDLCが主流になっていくと考えています。
その中でも今回の西東京データセンターは最先端の事例と言えます。国内のデータセンターでDLCを導入しているところはまだほとんどありません。もともとは空冷方式の設備でDLCを実現したというのは、間違いなく非常に先進的な取り組みだと言えます。


キヤノンITS 郡田:ありがとうございます。西東京データセンターについて簡単に説明しておくと、1号棟は2012年に竣工し、金融機関、製造業、流通業などさまざまな業種の方たちに使っていただけるよう、電力・空調能力を当時としてはかなり高く設計し、「JDCCティア4レベル」の安全性を備えた設備としました。さらに2020年に開設した2号棟は、将来的な電力・空調能力の高い需要を見越して1号棟の2倍ほどのIT電力供給能力を実現しています。床の耐荷重は1号棟で1平方メートルあたり1.5トン、2号棟はフロアによっては2トンとなっています。
1号棟、2号棟とも、メインフレームに液冷方式が使われたり、局所的に冷却するIn-Row空調機などを入れたりする可能性を考慮して、床には防水対策を施し、水の配管を回せるようにはなっています。とはいえ、多くのお客さまは電気と水という組み合わせを嫌がるものだったので、今日のように液冷方式、とくにDLCの需要が急速に高まることまでは予想していませんでした。

ティア4レベルの安全性を備えた西東京データセンターの液冷設備について
サーバールーム内の冷水供給

- 空冷モジュールチラー(冷却水循環装置) / N+3の冗長構成で14℃冷水を生成
- 冷水供給配管 / 2Nの冗長構成で冷水を供給
-
空調機 / N+1の冗長構成でサーバールームに冷風を供給
直接液冷方式(DLC)で冷却しきれないサーバー排熱(サーバー負荷の20~30%)を空冷で回収

- 室内配管への供給 /冷水供給配管から2Nで室内の配管に引き込み
- ループ配管方式 /障害点をバルブ閉止にて切り離した際も、冷水の供給を継続
- ラック毎に切離し /配管に切離しのためのバルブを設けることで、他のラックに影響なく障害ラックのみを切り離せる構成を実現
水冷方式の実績が豊富で信頼性が高いHPEと連携
HPEとキヤノンITSがタッグを組むに至った経緯についてお聞かせください。
キヤノンITS 南里:今回の案件のお客さまは、当初は空冷方式でのサーバー導入を検討されていました。それが選定直前まで進んでいたところ、お客さまのご要望をより満たせる液冷方式サーバーの導入案が浮上。そこで西東京データセンターでも設置できる環境を構築してほしいというご依頼があり、それに応えるかたちになりました。
お客さまのご意向を受けて、まず社内の技術部門に相談したのですが、ハードウェア的な要素が先進的な技術になるので私たちだけでは知見が足りず、どうしたものかと悩んでいました。そうした中、液冷方式に関して数十年におよぶ数多くの実績があり、信頼性が高く最先端の技術やサービスを提供されているHPEと連携できることになり、そこからいろいろ意見交換させていただくようになったという経緯があります。

DLCのデータセンターへの導入について、最初は不安があったそうですね。
HPE 杉田:米国のHPとキヤノンは長年にわたり多くの協業実績がありますが、キヤノンITSのデータセンター構築に携わるのは初めて。さらに、液冷方式に関しては絶対的な自信を持っていますが、データセンターをDLC導入のために改修する取り組みに直接携わった経験がなかったのです。しかし、この双方にとって初となるチャレンジへのキヤノンITSの積極果敢な姿勢に触発され、一緒にやることへの意欲が掻き立てられました。
複数の企業が利用するデータセンターは社会のインフラ的存在であり、各企業が自社で持っているデータセンターにサーバーを納入する際にとは求められる要件レベルの違いを強く意識していました。しかしコロケーションのデータセンターの場合は、何かあった際に影響を受けるお客さまが多数いらっしゃることを考慮する必要があります。
キヤノンITSとしてもかなり慎重にならざるを得ないわけで、プロジェクトの進め方としてお客さまも交えた三者で毎週、週次定例会を行いつつ、それとは別にHPEとキヤノンITSとで毎日のようにやり取りをしていました。

液冷方式によるサーバー冷却サービス
安心できる冷水供給設備

ティア4レベルの安全性を備えたDC設備をベースに、CPU室までの冷水配管は2N構成※。サーバーへの冷水供給に関しては、ループ配管方式を採用することで高い耐障害性を実現。また、障害発生(任意ラックでの漏水等)の場合は、該当部分を安全に切り離すことが可能で、他システムに影響が無い構成としています。
-
※
2N構成:システムを二重化し、冗長性を高めた構成。必要な機器や経路を2セット用意し、どちらか一方に障害が発生しても、もう一方でシステムを継続して稼働させることができます。
超高負荷サーバーに対応
直接液冷方式(Direct Liquid Cooling)サーバー100kW/ラックに対応。
“世の中に明確な答えがない”という大きなハードルが立ちはだかる
データセンターへのDLCの採用は、どのような点で難しかったのでしょうか。
HPE 松島:システム設計は私が担当しました。今回はDLCということで、電力量、耐荷重などサーバー自体の諸元のほか、サーバーを冷やすのに必要な水の温度や流量などについても、これまでの成功事例に基づいた情報をこちらからキヤノンITSに提出し、それに対して質問をいただいてさらに返答するといったことを、何度も繰り返して仕上げていきました。
空冷方式のサーバーであれば、極端に言うと電源さえあれば同じスペックのものを同じように入れることができるのですが、DLCの場合、設備側をオリジナルのものとして組み合わせてつくり上げなければなりません。
さらにデータセンターならではの高度な要件があるので、ハードウェアの技術的なところは私の方でカバーし、ファシリティの部分に関しては別の専門のエンジニアが携わっていました。そのようにHPE内でも多くの関係者を巻き込んで計画を立てる必要があり、通常の空冷方式のサーバーを導入するよりも検討すべき事項は多岐にわたりました。詳細な情報提供や密度の濃いコミュニケーションを含め、通常より多くの時間と工数を要しましたが、その分非常に達成感のある仕事ができたと感じています。

キヤノンITS 青木:国内では、データセンターでDLCのサーバーを置いている事例がほぼないため、世の中に参照できる明確な答えがないというのが、この案件を進める上でとても大きなハードルでした。
空冷方式を使いながらDLC設備を入れるので、空冷方式を妨げずに水の配管をどう通すか。導入する時に作業者がどうやって入るのか。さらに他のユーザーさまも利用されている中、どんな構成で配管設備などを構築すれば影響を最小限にできるのか。サーバーに問題が生じたため冷水供給を止めるといった最悪のケースも想定して、運用面でどう対処するか考えた上で配管の設計などを進めました。そして、その都度私たちの考えが適切かどうか、豊富な実績を持つHPEに意見を聞いたり、HPEがDLCのサーバーを納品されたユーザーさまの施設を見学させていただいたりして、答えを探していった感じです。

キヤノンITS 八木:データセンターの第一の使命は、お預かりしているサーバーを日々安全に運用することにあります。ですからハードウェアのデザインだけでなく、もしものケースにも対応できる運用設計をしなければいけません。
そういうことも含めて、かなりしつこく松島さんや杉田さんに質問したり、実際に数多くの設備を担当されている液冷方式のスペシャリストの方に話を聞いたりしました。そうやって一つひとつ確認させてもらうことで、なんとか前に進んでいくことができたと思っています。

業務に対する真剣な向き合いがお互いの信頼関係を築いた
DLCのプロフェッショナルであるHPEと、データセンターのプロフェッショナルであるキヤノンITSの両者によるプロジェクトとなりましたが、実際に進めてみての感触はいかがでしたか。
HPE 杉田:キヤノンITSの方で詳細な課題管理表をつくられていて、多くの質問をいただきました。詳細な質問も少なくなかったのですが、その積み重ねが安心材料になりました。
キヤノンITS 青木:初めての取り組みで、私たちもなりふり構わず必死でした。こちらが適切なものを準備できなければラックを設置することができませんし、そうなるとHPEも作業ができず、プロジェクトが終わらなくなってしまう。何としてもやり遂げなければ、という思いでした。
HPE 杉田:キヤノンITSの方が細部にまで気を配っている様子から、改修を成功させたいという熱意を感じていました。自分たちがより良いものをつくり上げるための質問であることをが伝わってきたので、信頼感の醸成につながりました。
キヤノンITS 八木:質問をバンバン投げて、せめぎ合いのように日々の業務が進んでいったのですが、お互いが真剣に仕事に向き合っているので、やり取りの中で自然と信頼関係が生まれていったように思います。言い訳ではないのですが、とにかく時間がなかったんです。設計をいつまでにまとめなきゃいけないとか、それができなければお客さまが望むゴールに間に合わないということで、遠慮する余裕もなく、気になることがあったらすぐHPEに確認しよう、という感じでした。
DLCに一歩踏み出すのは、本当にすごく勇気がいること
いちばん苦労されたのは、やはりスケジュール管理ですか。
HPE 杉田:プロジェクトの期限が変わらない中、空冷方式からDLCへの仕様変更に対応するためのスケジュール調整に苦労しました。ゴールが決まっている中で、お互いの役割を果たしながら実現する方策を本気で考え、対応し、遅延なくやり遂げました。
キヤノンITS 八木:もともと非常にタイトなスケジュールで、私たちとしては12月中にラックを置ければいいと考えていたのですが、後からHPEとお客さまの検証作業に時間がかかることがわかって、12月では間に合わないことが判明しました。そこで、キヤノンITSが工事業者間の調整を行い、なんとか11月の頭にはサーバーを設置できるようにし、HPEが自社の検証作業、お客さまとの検証作業を調整して短縮することにより、12月末のサービス開始を実現しました。
キヤノンITS 南里:私自身も営業として、当初は本当に期限内に提供しきれるのか心配していました。おかげさまで無事にプロジェクトが完了し、お客さまに完成した設備をご覧いただいて、この短期間で冗長性や堅牢性もしっかり満たせたものが出来上がっていると、改めて良い評価をいただけたと認識しています。
HPE 松島:どちらも最終的にはお客さまのためという思いがあって、キヤノンITSは、インフラのデータセンターの部分で、私たちはサーバーを提供する立場で、共に同じゴールに向かって取り組むことができました。システムが無事にカットオーバーしてお客さまが運用に入っていただけるよう、一丸となってプロジェクトを推進していったと実感しています。
HPE 杉田:印象的だったのが、プロジェクトがある程度進んだ段階で、キヤノンITSサイドから実際に現物を見てみたいと依頼され、HPEがサーバーを納品している国立の研究機関の施設を見学する手配をした際の様子です。キヤノンITSは非常に熱心で、床に這いつくばって床板を開けたり、さまざまな質問をして、一つひとつ確認したりしていました。
キヤノンITS 八木:あの時点ではデザインがだいたい完成していて、机上の確認ではそれが正しいと思っていました。しかし、実績のない設備のデザインだったため、本当にそれが正しいのかを確認したかったのです。床下の配管を見せてもらって、これは何ですか、どういう風に接続されているんですかとか、いくらでも聞きたいことが出てきて、たくさん質問してしまいました。HPEの最先端の技術が実際に運用されている現場を見させていただき、大変参考になりました。
HPE 皆川:DLC導入のために一歩踏み出すことは、本当にすごく勇気がいることなんですよね。多くのデータセンター事業は、既存の施設を改修することには踏み出せないわけです。
キヤノンITS 郡田:それからもう一つ、データセンターの既存のお客さまの反応もとても心配でした。施設内に水を入れることを嫌うお客さまも多いだろうと考え、いかに徹底した対策をとっているかを説明する準備をしていたのですが、液冷方式が普及期に入って広く認知されるようになったためか、とくにお客さまから言われることもなく、少しほっとしました。
DLC 運用事例

DLCは設備に求められる要件が厳しく、安定した運用にはデータセンター事業者の高い技術力が要求されます。キヤノンITSのデータセンターではHPEとの連携のもと、2024年12月より、直接液冷(Direct Liquid Cooling= DLC)を搭載した高密度型サーバー「HPE Cray XD2000」の運用を開始しています。DLCを搭載した液冷サーバーは、リアドア等を用いたハイブリッド液冷とは異なりGPU、CPU、メモリモジュールなどのコンポーネント上に冷却液を直接流すことで、強力な冷却を達成できます。
DLCに対応できるデータセンターが、お客さまの事業の可能性を広げる
DLCに対応できるデータセンターの意義について、改めてお聞かせください。
HPE 皆川:最先端のことをやりたいお客さまはたくさんいらっしゃると思いますが、そのためには最先端のインフラが必要なんですよね。広範な普及が始まったDLCという冷却機構を備えた最先端のサーバーを自社データセンターに置けるかといったら、普通は難しいはずです。そういった時、DLCのデータセンターがあって、それを利用できるというのはすごく魅力的なことだと考えています。とくに日本は電力が逼迫しており、効率よく電気を使うという意味でもこれから液冷方式の普及・導入がマストになってきます。それに合わせて、液冷方式に対応できるデータセンターの存在意義もより大きくなっていくでしょう。
キヤノンITS 郡田:貴重な電力を効率よく使い、HPEの優れたサーバーの性能を100%引き出せる設備をご用意できることは、データセンターにおいて「広さ」から「消費電力」を競う時代へと変わる中、その事業者としての私どもの新たな価値になると思っています。データセンターに対する多様なニーズがある中で、大きなリソースが必要なお客さまに対してDLCのソリューションをご提案できることで、お客さまとの「共想共創」が広がることを期待しています。
HPE 松島:冷却方式を従来の空冷方式からDLCにすることは、省エネルギーという観点で社会貢献にもつながります。ただし、それには大きな投資が必要なわけです。今回、キヤノンITSが思い切った投資をされて、それに対して私たちもDLCのサーバーを納品させていただいて実績をつくることができました。一つひとつは小さなことかもしれませんが、こうした取り組みがどんどん広がることで大きな社会貢献になっていくのではないかと思います。
HPE 杉田:私はこのチームであれば、新たな課題があったとしても一緒になって解決できるのではないのかという気がしています。単なる技術論ではなく、共に困難を乗り越えて、日本での広範な普及が始まったDLC対応のデータセンターを実現した。そんな経験を共有しているからこそ、私たちならどんなことがあっても気持ちを一つにして何かを成し遂げられる自信がありますし、いろんなことに挑戦ができると思っています。
キヤノンITS 郡田:うれしいお言葉をありがとうございます。これからもHPEと力を合わせ、「共想共創」の精神でお客さまの想いを共にかたちにしていけたらと願っております。
本日はありがとうございました。
詳しくは、こちらのコンテンツもご覧ください
西東京データセンター
高性能なGPUサーバにも対応した液冷方式によるハウジングサービスを提供。
世界基準の運営品質のデータセンターをもっと身近に
液冷サーバ導入の課題に対するソリューションとして、液冷サーバ対応のハウジングサービスを西東京データセンターにて提供しています。短納期でGPUサーバ・HPCサーバに適したITインフラ環境を提供します。
自然災害の影響を受けにくい武蔵野台地に立地した西東京データセンターは「ティア4レベルの高性能ファシリティ」、「世界基準の運営品質」、「充実したSEサービス」が評価され、金融業、製造業、クラウド事業者など数多くの企業にご利用頂いております。高性能なGPUサーバにも対応した液冷方式によるハウジングサービスも提供しております。





