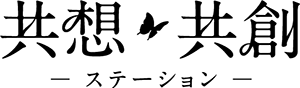 “100年企業”が統合データベース構築で切り拓く!配置薬とドラッグストア、そしてECをつなぐ道Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み
“100年企業”が統合データベース構築で切り拓く!配置薬とドラッグストア、そしてECをつなぐ道Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み
公開日:2025年10月23日
キヤノンITソリューションズ株式会社 デジタルソリューション開発本部 デジタルビジネス開発部 北防 拓也(以下、本文は敬称略)

近年、医薬品販売の分野においても、DXは不可避的にして喫緊の課題に。配置薬というトラディショナルな事業を原点とし、ドラッグストア、調剤、製薬、そしてECと多角的な経営を展開してきた株式会社富士薬品も今、大いなる変革のさなかにあります。2030年の創業100周年を前に、全社を挙げてのDX戦略が本格始動。“100年企業”のレガシー――個々のお客さまに寄り添い続けてきた実績、そこから得られた知見の蓄積をさらに活用し、製販一貫体制と複数チャネルというアドバンテージをより強固にしていく。その果敢な挑戦にキヤノンITSも参画し、共に走り続けています。老舗企業ゆえの課題、すなわち事業ごとに個別最適化され運用されてきた諸データを統合するデータベースの構築から始まったDX、そしてその先にある未来のかたちについて、同社DX戦略推進本部の岩田 裕樹 様と弊社デジタルソリューション開発本部の北防 拓也が語り合いました。
100年に迫る歴史を誇る複合型医薬品企業
本日はこのような機会をいただき感謝申し上げます。はじめに貴社の事業内容について、お聞かせいただけますか。
岩田:富士薬品は、医薬品の製造から小売までを一貫して行う複合型医薬品企業です。配置薬販売を祖業として1930年に創業しており、2030年には100周年を迎えます。「富山の置き薬」の精神を引き継ぐ配置薬販売事業は、お客さまのご自宅やオフィスなどに薬箱を置かせていただき、使った分だけお支払いいただくというビジネスモデルです。現在、配置薬をご利用のお客さまは北海道から沖縄まで全国に約250万軒 、それを約1,500人の営業員で担当しています。定期的にお客さま先を訪問して、対面での接客を通じてそれぞれのご家庭などの状況を把握し、適正な医薬品・健康食品を計画的にお届けしています。
1992年には、新たな販売チャネルとしてドラッグストア事業に進出。「セイムス」を中心に拡大を続け、今日では富士薬品グループ全体で約1,270店舗を展開するまでになり、当社の主力事業へと成長しました。近年は調剤事業にも注力し、調剤取扱店舗率は上昇傾向にあります。私どもはドラッグストアを「インターネットの情報以上、病院未満」と位置付け、“Google以上、ドクター未満”というキャッチフレーズのもと、薬の説明だけでなく、ヘルスケア、ビューティーケアのカウンセリングなどもいっそうの充実に取り組んでいます。それらにより、地域に根差したプライマリケアを提供し、お客さまに「富士薬品のドラッグストアに来れば、いつでも気軽に健康相談ができる」と思っていただける存在にしていきたいと考えております。
医薬品の製造については、配置薬事業を持続的に成長させる上で自社製品を持つことが必要だと考えた創業者が、1986年に富山工場を立ち上げて製販一貫体制を確立しました。現在、富士薬品ブランドとして196商品を生産するほか、第二工場は米国FDA(食品医薬品局)認証を取得したグローバル対応の医薬品工場として、医療用注射剤を受託製造しています。




現代においてもなお、配置薬が必要とされる理由
多角的に事業を展開される中でも、創業から続く配置薬販売を大切にされていらっしゃいますが、配置薬はどういった点で優れているのでしょうか。
岩田:何と言っても、営業員 がお客さまのもとに直接お薬をお届けするというのが配置薬販売の大きな特徴です。お宅へ伺い、健康や暮らしの困りごとについてのお話をじっくりお聴きしながら、それぞれの状況に合わせた最適なお薬やアドバイスをきめ細かに提供することができる。そんな風に、お客さまとの信頼関係を継続的に築けるのは配置薬ならではの長所です。また、お客さまにとって、家にいつでも薬があるという安心感は決して小さくないと思います。実際、コロナ禍で容易に外出できなかった時期などには、「配置薬があってよかった」というお声をたくさんいただきました。
北防:この配置薬事業を基点として、自治体との連携協定も増えているそうですね。
岩田:当社は医薬品企業として社会に貢献することを使命と考えており、例えば大きな災害などがあった際には、代金をいただかずに配置薬を自由に使っていただいています。先般の能登の震災でも配置薬を無償提供し、地域の方々のお役に立つことができました。そうした活動による地域貢献が認知されるようになり、2022年以降、複数の自治体と包括連携協定を結んでいます。役所などへの配置薬の設置や災害時の医薬品の無償提供をはじめ、高齢者の見守りや健康セミナーの開催などさまざまな活動を通して、安心・安全な暮らしや健康づくりの支援を進めており、今後連携させていただく自治体が増えていく見込みです。
北防:昨年 8月から始まった処方箋応需手段の試験運用とは、どんな取り組みですか。
岩田:調剤店舗と配置事業との連携による試みです。交通手段が限られるような地域では、総合病院へ行って薬局で薬を受け取って帰ることが時間的に大きな負担になるケースがあります。そこで、配置薬をご利用のお客さまが持ち帰った処方箋を営業員 が預かり、富士薬品グループの調剤店舗で薬を調剤してお客さまにお届けするというサービスを試験的に運用しています。これからの配置薬事業は、同じ富士薬品グループのドラッグストアや調剤薬局との連携を強化し、お客さまのニーズに応えて必要な時に必要なものをお届けできるようになることを目指しています。そのためにも今、DXを戦略的に推し進めることが重要なのです。

線から面へ、そして「ワントゥーワン」サービスの実現へ
2023年に社長直轄組織としてDX戦略推進本部が設置されたそうですが、その背景にはどのような課題があったのでしょうか。
岩田:冒頭でお話ししたように製販一貫体制は当社の強みなのですが、システムに関してはバラバラで、それぞれの事業部が個別にデータを管理している状況でした。とくに配置薬とドラッグストア、さらに公式通販のECサイトというタイプの異なる販売チャネルを持ちながら、事業が縦割りになっており、お客さまの情報も一切共有されていませんでした。そのことに以前から危機感を持っていた社長が呼びかけ、創業100周年に向けて全社DX戦略を考えるチームが発足。情報システム部をはじめ各事業部から選ばれたメンバーが、「これからの富士薬品のDXはどうあるべきか」を真剣にディスカッションし、ロードマップをつくりました。このDX戦略を実際に遂行していくために組織されたのがDX戦略推進本部です。
北防:あらためて、貴社全体としてどのような見取り図のもとにDXを進めようとされているのか、ご説明いただけますか。
岩田:生産、配置薬、ドラッグストアそれぞれのラインで個別に動いているものを統合し、富士薬品グループという一つの「面」として成果を上げられるように支援するというのが弊社のDXの大きな目的です。まずは各販売チャネルのデータを集めて共通化し、一人ひとりのお客さまに対して富士薬品全体として適正な付加価値を提供していくことを目標としています。ドラッグストアと配置薬で扱っている商品やサービスがまるで違うというのも、同じ会社として矛盾と言えます。そこをできるだけ揃えていき、最終的にはどのような手段であっても同じように「ワントゥーワン(One to One)」のサービスを提供できる体制をつくり上げる。それが長期的に見た弊社のDX戦略のゴールです。
北防:日々の業務において具体的に課題に感じていたことはございますか。
岩田:ドラッグストアでは、お買い上げいただいたすべてのお客さまにPOSレジで同じクーポンを発行しているのですが、なかなか使っていただけないケースが多く、あまり効果的とは言えない状況でした。そのため、販売チャネルの垣根を越えてお客さまのお買い上げ情報を分析し、アプリでの付与も含めて一人ひとりに適したクーポンをお届けしたいというのが、DX戦略を進める直接的なきっかけの一つだったのです。

はじめにデータ一元化ありき――統合データベースを共創する
それではここで、事業間統合データベースの概要についてお聞かせください。その構築プロジェクトにおいて、どんな「共想共創」が行われていたのでしょうか。
北防:これは長期的なDX戦略のための基盤構築という位置付けでしたね。いわば土壌づくりとでも申しましょうか……。
岩田:ええ。DX戦略チームでデータを利活用しようにも、そもそも使えるデータがありませんでしたから。前述の通り、事業部ごとに情報が分散していましたので、まずはそれらを集約・一元化して使えるようにする必要がありました。文字通り、DX戦略の「初めの一歩」として事業間統合データベース構築のプロジェクトを立ち上げたのです。プロジェクトを進めるに当たっては、複数のベンダーさんに声がけしてコンペを実施しましたが、中でもキヤノンITSさんには技術や経験に裏付けられた自信、そして安心感を強く感じました。
何よりキヤノンITSさんは、プロジェクトのマネジメントにおいて非常に頼れる存在でした。今回、情報システム部門は人手が足りず社内でPMを立てる余裕がなかったため、弊社側のプロジェクトのタスク管理もお願いした次第なのですが、「進捗がちょっと遅れてますよ」とか、「そろそろこういうアクションが必要ですよ」といった指摘や助言をこまめにしてもらって助かりました。基盤の運用はすべてお任せし、我々は本来の業務であるデータ活用に注力できるということで、キヤノンITSさんにお願いして本当によかったと思っています。
北防:そうした社内事情までは事前に存じ上げなかったのですが、我々が持つ事業間統合データベースの構築に関する知見を活かし、適切なソリューションを提供できればという思いは当初からありました。私自身、データ統合の経験がありましたので、過去の仕事で得た情報を自分の中で整理して、何か問題が生じた際にもすぐにお答えできるように準備して臨んだつもりです。
今回の事業間統合データベースはあくまで全社DX戦略のための基盤整備です。集まったデータをどう活かされていくかについてはまだ構想が固まっておられないということでしたので、我々としては先々どういった使われ方をするのかを想定して、さまざまなシチュエーションに適応できるものをつくることを強く意識しました。手前味噌になりますが、この辺りが「共想共創」が実現できたと言える部分なのかもしれません。
岩田:おっしゃる通り、しっかり計画が出来上がっていたわけではないので、リクエストが変わる前提でシステムを組み上げていってほしいとお願いしました。「ここは汎用的にしてほしい」とか、「一個一個をパーツ化したい」といったことを何度も何度も相談し、その度に北防さんを悩ませてしまいましたが(笑)、どんな変化にも柔軟に対応し、対話を重ねながら落としどころを考えてくれるのがキヤノンITSさんの素晴らしさだと感じています。

データマネジメントサービスについて

消費者ニーズやビジネス市場の変化に柔軟に対応するためには「データ活用」が必要です。そのデータ活用には、データとデータを活かせる人材が重要です。
ビジネス変革に効果的なデータ活用には、活用の目的に沿ったデータを整備し、そのデータを蓄積する仕組みを作る必要があります。かつデータを分析しインサイト(本質を突いた気付きや洞察)を得るためのデジタル人材が欠かせません。
キヤノンITソリューションズは、データを整備・活用する仕組みを構築し、「価値あるデータ」と「データを活かせる人材(デジタル人材)」の創造を『データマネジメントサービス』として提供することで、お客さまのDX実現を支援します。
徹底したPOCと「捨てる提案」で進行をスムーズに
実際に統合作業を進める上で、ポイントや障壁となったのはどんなところだったのでしょうか。
北防:プロジェクトの進め方としては、最初の4、5カ月ほどを使ってPOCを行い、その中でさまざまな検証作業を行いました。例えば先々、スマホアプリなどから既存のデータを使って個人にパーソナライズした仕掛けを展開していくことを考え、それに耐えうる基盤になっているか否かというところについては、かなり念入りに検証させていただきました。
岩田:我々としては、やることが明確に決まっていない分、ついいろいろと盛り込みたくなってしまうのですが、POCにおいてキヤノンITSさん側から、「これは必ずしも今すぐやらなくてもいいのではないですか」と、「捨てる提案」をしてもらえたのもありがたかったですね。おかげさまで、結果的に無駄なコストや作業を減らすことができました。
北防:今回大変だったのは、別々なところで管理されていたこともあり、取り込むデータの形式にかなりのばらつきがあった点ですね。データ活用を視野に入れると、きれいに整形された情報でなければデータの汎用性が失われ、ひいては信頼性も崩れてきます。取り込み作業をしながら、イレギュラーなデータが出てくる度、「これはどうしましょうか」と一つひとつご相談しながら処理していったことが記憶に残っています。
岩田:昔はお客さまに店頭で紙に書いて会員登録をしていただいたり、配置薬も申込書に手書きしていただいたりしていたため、文字の読み間違いや記入ミスなどもよくありました。また、行政による区画整理があると住所表記が変わってしまうため、正しくお客さまを認識することができなくなるといったケースも多々ありました。
北防:住所については、漢字で書いたりハイフンを使ったりといった表記の揺れの問題もあり、郵便番号と住所の何丁目、何番といった情報だけを取り出してコード化する技術を用いて統一していきました。それから、配置薬とドラッグストアの顧客を統合していく際には名寄せが必要ですが、例えば電話番号が一致するとか、住所が一致するとかといった条件を定めて、最初にどれくらい実現できるかをPOCの間にシミュレーションしました。その結果を見てご相談しながら、実際に名寄せする方法を決めていきました。
岩田:ドラッグストアのデータは1カ月分で億単位のレコードになってしまうので、取り込むだけでも時間がかかって大変でしたね。
北防:事前に大体の時間を計算してスケジュールを組んでいたのですが、例えば先ほど述べた住所情報の加工・統一のような作業が入ってくると、どんどん時間を消費してしまいます。その都度時間を短縮する手段を考えてはご提案することを繰り返し、今は順調に運用いただけるようになりました。

配置薬とドラッグストア――大河の両岸に橋を架けるDXの先にあるもの
今後のDX戦略の展開やビジョンについてお聞かせください。
岩田:今回、事業間の統合データベースを構築したことで、DX戦略を推し進める基盤ができたことは大きな成果です。しかし、全体から見ればまだまだ取り込めていないデータも多い。今後もキヤノンITSさんの知恵もお借りしながら、できるだけ早くあらゆるデータを集約し、一つのまとまった情報源として誰もが使いやすいデータベースを構築していきたいと思います。
北防:この先、富士薬品さん が統合データベースに格納されたデータをどう営業戦略に活用していかれるのか、非常に楽しみで個人的にも興味を持っております。例えば、配置薬のお客さまがどこのセイムスで何を購入しているのかといった顧客動向がスピーディーにつかめるようになり、先ほどおっしゃっていたクーポン配布の最適化など、お客さま一人ひとりに向けた具体的で効果的なアプローチがどんどん可能になっていくのではないでしょうか。
岩田:そうですね。ようやく統合データベース上に配置薬やドラッグストア、ECの情報が揃ってきていますので、これらの情報を正しく分析して、それぞれのお客さまに必要なクーポンや販促情報を届けられる仕組みを早急につくっていきたいと思います。この先の目標としては、自社製品の生産側の情報を統合し、サプライチェーン全体を整地していって、在庫の適正化なども図っていきたいところです。
北防:生産から販売まで一貫していて、しかも販売チャネルを複数持っておられることは、間違いなく富士薬品さまの強みだと思います。我々といたしましても、この貴社ならではのアドバンテージをさらに高めていくお手伝いができれば幸いです。
岩田:事業間をまたいだデータベースを利用できるというのは、他のドラッグストア事業者との大きな差別化ポイントであり、それこそが当社の「尖った」部分になるのだろうと思っています。配置薬の営業員は、お客さまのお宅にお邪魔し、お悩みやご希望を直接うかがうことができる。そういった声をきちんと拾い上げて、店舗運営なり自社製品の開発に活かせるようなサイクルが築ければ、状況は今より確実に良くなると思います。そうした循環の核となるのが、今回の統合データベースなのです。
北防:DX戦略を進めることで、配置薬のお客さまが新たに近在のドラッグストアを利用するようになったり、ドラッグストアの品ぞろえに配置薬のお客さまの声が反映されたりといったシナジー効果も生まれそうですね。
岩田:それはぜひとも実現していきたいところです。現状では配置薬のお客さまのうち半数もドラッグストアの顧客と重なっていませんが、その数をどんどん増やしていこうという試みをDX戦略チームが中心となって進めています。富士薬品のロイヤルカスタマーは、やはり配置薬を使っていただいているお客さま。そのことをしっかりと再認識し、大切にしながら進めていきたいです。
北防:私自身、年齢を重ねるにつれて健康というものを強く意識するようになりました。長年にわたり地域に寄り添い、人々の健康を守り続けてきた富士薬品さまとお仕事ができてとても光栄です。
岩田:創業100周年に向けてのメッセージに、「人の健康と暮らしを支えていくのが富士薬品の役割である」とうたわれています。その実現に向けて、会社もシステムも柔軟かつ果敢に変わっていきながら、これから先の100年もさまざまなお客さまに選ばれる存在であり続けたい。そんな思いで私たちは日々活動しています。キヤノンITSさんにはこれからもよきパートナーとして、私たちと伴走していただければと思います。
北防:よりいっそう統合データベースを充実させて、貴社のDX戦略の成功、ひいては顧客の皆さまのQOLの充実に向けて、さまざまな角度からお役に立っていきたいと考えております。本日は貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。

お客さまプロフィール
- 会社名
- 株式会社富士薬品
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地



