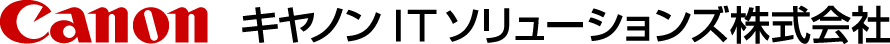攻めのデータ戦略
- 特別企画
ビッグデータ活用のビジネスモデルを再考する
ビッグデータ活用に取り組んでいるものの、思うような成果が上がっていないーー。最近、そんな声をよく聞く。準備が足りないのか、それとも活用の仕方に問題があるのか。一度立ち止まって、自社の組織の文化や構造、ビジネスモデルについて考え直してみる必要があるのではないか。この分野で数々の実証実験やプロジェクトに関わってきた国立情報学研究所 所長補佐 情報社会相関研究系教授、佐藤一郎氏の話を基に、ビッグデータ活用へのアプローチを考えてみたい。
ビジネス目的を起点にデータ活用を考える
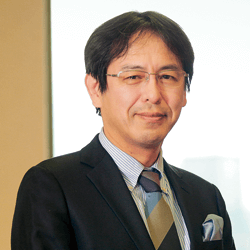
国立情報学研究所 所長補佐
情報社会相関研究系 教授
佐藤 一郎 氏
Ichiro Satoh
日本のメディアに“ビッグデータ”という言葉が現れたのは、2010年前後のことである。10年近くが経過した今、多くの企業がビッグデータ活用に向けた施策を講じている。しかし、思うような成果が上がらぬまま、進むべき道を探しあぐねているケースも少なくないようだ。
そもそも、何のためにデータを役立てるのか、自社のビジネスにおけるデータの意味とはーー。場合によっては、いったん立ち止まって考えてみる必要があるだろう。
ビッグデータが注目されるようになった背景について、国立情報学研究所 所長補佐 情報社会相関研究系 教授の佐藤一郎氏は「マーケティングの変化が大きい」と指摘する。
「大量生産・大量消費の時代、市場ニーズを把握するための手段としては、サンプリング調査などが用いられました。多くの人たちが同じような商品を買っていたので、当時はそれで十分でした。しかし、今ではマス市場を前提にしたマーケティングは通用しません。多くの消費者が企業のCMよりも、クチコミサイトを信用する時代です。こうした環境変化を受けて、企業は個々の顧客の行動を追跡、分析する必要性を感じるようになりました。個々の顧客の動きを見るのですから、扱うデータの量は増大します」
業種・業態によっては、顧客の均質性が高い分野もある。「マーケティング向け利用に関しては、顧客ごとの違いがさほど大きくない場合、ビッグデータ活用はさほど有効とはいえないでしょう」と佐藤氏は続ける。
ビッグデータ活用が期待される分野は、研究開発やスマートファクトリー、サプライチェーンなど幅広い。どのような分野に適用するにしても、「ビジネス目的を起点に考えるべき」と佐藤氏は強調する。
佐藤氏の元には、企業からさまざまな相談が寄せられるという。
「よくあるのは『うちにはたくさんデータがあります。分析すれば、きっと何かに使えるはず』というパターンです。つまり、目的があってデータを集めているわけではなく、たまたまデータがあるから活用したいということ。このようなアプローチでは、大きな成果は期待できないように思います」
データを生かすためのマインドの組織文化
データ収集の仕組みは、何らかの目的に従ってつくられている。佐藤氏が挙げた例はPOS(Point Of Sale)データである。POSデータによってメーカーや商品名などを把握できるが、パッケージの違いを識別することはできない。
「例えば、マーケティング担当者がパッケージデザインを変えて、A/Bテストをやりたいと思っても、POSデータは役に立ちません。もともとそのような目的は考慮されていないからです」
逆に、目的が明確なら、知恵と工夫次第でスモールデータを最大限に生かすことができる。佐藤氏にはこんな経験があるという。
「小売事業者からショッピングモールへの出店の相談を受けたことがあります。客層が分からないので協力してほしい、とのことでした。実は客層を見るデータは我々の周囲に散在します。私が注目したのは飲料の自販機です。自販機の補充を担当するスタッフの給料は、多くの場合、売り上げとほぼ連動します。そこで、スタッフは飲料の入れ替えなどを試しながら、売り上げの最大化を目指しており、設置から1年もすると、自販機にはその設置場所に最適化された飲料が並びます。つまり、近隣の自販機の品ぞろえを見れば、ショッピングモールの客層を推定することができるのです」
例えば、フレーバーティーのような飲み物が多ければ、若い女性の比率が高い。あるいは、炭酸飲料が多いようなら、若者の比率が高いと考えられる。
このとき佐藤氏が用いたのは、コンピュータにため込んだデータではない。人間への観察力であり、ビジネスに対する洞察力である。物事を突き詰めて考えようとするマインドと言ってもいい。こうした姿勢が身に付いていれば、少量のデータでも有効活用できる。その延長上に、ビッグデータの活用がある。
マインドに加えて、組織文化の面での課題もあると佐藤氏は考えている。キーワードは現場裁量だ。
「従来のBI(Business Intelligence)を含めて統計分析はマクロ的だが、ビッグデータではどちらかというとミクロの分析に向いており、大きな意思決定のためというより、現場判断をサポートするという使い方がメインになります。つまり、ビッグデータを活用するのは、主に現場の人たちです。現場裁量が認められた組織ほど、ビッグデータを活用しやすいといえるでしょう」
例えば、同じ小売チェーンでも、店長の裁量が大きな店舗はビッグデータを見ながら柔軟に棚割りを変更することができる。逆に、本部主導であり、現場裁量が小さければ、ビッグデータを活かした店づくりは難しくなる。
多くの場合、ビッグデータはAIとセットで論じられる。人間の手に余るほどデータ量が増えれば、AIを組み合わせるのは自然な流れだろう。大量データを処理するためのAIのアルゴリズム、コンピュータの処理能力は急速に進化している。AIとの関連でいえば、データの量は非常に重要と佐藤氏は話す。
「機械学習や深層学習といったAI的な手法を使って、ビジネスを変革したいと考えているならビッグデータは欠かせません。学習用データの量がAIの質に直結するからです」
ビッグデータとAIを活用することで、精緻な売上予測が可能になる。小売業であれば過去の売上情報や天候情報、将来の天気予報などの情報を参考にすることで、売上予測の精度を高め機会損失や廃棄ロスなどを減らすことができる。ただ、ビジネスモデルによって、予測を最大限に生かせる企業、そうでない企業があることに注意する必要があると佐藤氏は言う。
「衣料製品を販売している企業を例に取ると、垂直統合モデルかどうかによって大きな違いがあります。垂直統合モデルなら、発売当初の販売数をみることで、早い段階で工場に伝えて増減産などの手を打てるでしょう。逆に、小売りと問屋、工場などの機能が分かれている場合には、迅速な情報共有は難しく、データがあっても、スピード感のある施策を実行しにくくなります」
ビッグデータ活用を推進するためには、組織の構造や文化まで踏み込んで考える必要がある。
サービス化の潮流、「POSからPOUへ」
ところで、今、多くの企業が新しいビジネスモデルづくりを目指している。1つの重要なポイントが「モノからコトへ」、言い換えれば「サービス化」である。この動きはビッグデータと密接に関係している。
例えば、クラウドコンピューティング。以前は、物理的なハードウェアとソフトウェアのライセンスを購入していたユーザーの多くが、クラウドサービスを利用するようになった。アマゾンやグーグルなどクラウドの巨人は、ビッグデータをテコに競争力を一層高めている。
同じことがあらゆる分野で起きつつある。自動車について言えば、シェアリングサービスや自動運転が広がれば、提供価値の多くをサービスが占めるようになるだろう。ビッグデータは、こうしたサービスの成否の鍵を握る。
「『モノを売って終わり』であれば、収集するデータは限られます。ITの性能的な限界から、販売状況、つまりPOSしか扱えませんでしたが、ビッグデータ向け技術の進歩により、商品の利用状況を逐一知ることが可能になりなす。いわば、『POSからPOU(Point Of Use)へ』。これによりデータ量も一気に増えますが、同時に商品販売からサービスにビジネスを変換できることになります。商品開発でも、従来の販売状況に基づいた商品企画から、利用状況を鑑みたものに変わりますし、商品の利用状況から得られたデータが新しいビジネスを生み出す可能性があります。今後、多様な業種で『POSからPOUへ』の移行と、そのPOUを活かしたビジネスは必須になるはずです」(佐藤氏)

サービス化の進展とビッグデータ
ビッグデータを競争力強化につなげるために、企業はどのようなポイントに留意すべきだろうか。多くの企業が新しいビジネスやサービスの創出を目指しているが、これはややハードルが高いと佐藤氏は見る。
「もうかるビジネスのアイデアは容易には生まれません。『これだ』というアイデアが浮かんでも、大抵の場合は他社が先んじています。むしろ損を減らすことを狙う方が確実かつ効率的です。ビッグデータを早い時期から活用していたのはネットゲームの事業者です。ユーザーの動きを学習用データとして取り込んで、離脱パターンを見つけ出す。そして、『そろそろ飽きてきた』と思われるユーザーに対して、ポイントなどの特典を提供して引き止めていました。クレジットカード会社は行動パターンを抽出して、不正利用を発見しムダな支出を抑えています。医療データから患者の状態を把握し、病気の前兆を発見するといった使い方もあるでしょう」
ここで気を付けたいのは、「誰の」損失やコストにフォーカスするかである。自社だけでなく顧客のコストまで視野に入れることで、ビッグデータ活用の幅は広がる。ビジネスの内容にもよるが、社会的なコストまでスコープを広げられるかもしれない。顧客のコスト削減支援の例として、佐藤氏はリース会社を挙げる。
「リース会社が提供している機器類のデータを収集し顧客の利用状況を把握できれば、その利用を最適化するための提案ができます。もしリース品が過剰に設置されているようなら、『今、10台設置されていますが、2台減らしても問題ありません』と言うこともできる。目先の利益は減りますが、顧客からの信頼獲得につながります」
今後、ビジネスのサービス化が進めば、こうした視点はますます重要になる。ネットゲームがそうであるように、サービスビジネスにおいて恐れるべきは顧客の喪失だ。たとえ一時的な収入減になったとしても、長い付き合いを続けることが顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高め、企業に中長期的な成長をもたらす。
サービス化は、企業の在り方そのものへの問い直しを迫る大きな変化だ。従来、毎月の売り上げという指標で評価されていた営業部門は、別の指標を工夫しなければならないかもしれない。経営の観点から見ると、顧客の元に届けたモノは顧客の所有物ではなく、自社のバランスシートに載るというケースが増えるだろう。
こうした大きな変化への準備ができている企業は、おそらく少ないのではないか。ビッグデータを価値に変えようとする企業は、そのビッグデータを基に自社の組織やビジネスモデルを変えることができるか、あらためて向き合う必要がありそうだ。「ビッグデータは部分最適化ではなく全体最適化で考え、自社のビジネスだけでなく社会全体の役に立つように大量データの分析を活用していただければと思います」(佐藤氏)
1996年慶應義塾大学理工学研究科大学院計算機科学専攻後期博士課程修了。博士(工学)。2001年国立情報学研究所ソフトウェア研究系助教授を経て、2006年から現職。平成18年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 若手科学者賞など受賞多数。内閣官房・政府IT総合戦略本部パーソナルデータ検討会・技術検討ワーキング委員など多数歴任。総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授も務める。
※ 記事中のデータ、人物の所属・役職などは、記事掲載当時のものです。