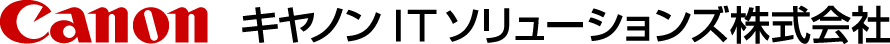「2025年の崖」の先には明るい未来がある
- 対談
既存システムを刷新すれば日本企業の強みがもっと生かせる

(写真左)
経済産業省 製造産業局
参事官(デジタルトランス
フォーメーション・イノベーション担当)
(併)ものづくり政策審議室長
中野 剛志 氏
Takeshi Nakano
(写真右)
キヤノンITソリューションズ株式会社
代表取締役社長
金澤 明
Akira Kanazawa
2018年9月に経済産業省が発表した『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』は、世の中に大きなインパクトを与えた。DXに取り組む日本企業にとって、複雑化した既存システムが大きな障害となっていて、2025年までにそれを克服しないと、デジタル化の大きな波に乗り遅れると警告したからだ。こうした状況をキヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)はどう受け止め、ユーザー企業のために何をすべきなのか。中心となってレポートをまとめ上げた経済産業省参事官の中野剛志氏と弊社代表取締役社長の金澤明が語り合った。(以下、敬称略)
DXを阻む原因はレガシーにあった

キヤノンITソリューションズ株式会社
代表取締役社長
金澤 明
Akira Kanazawa
金澤中野さんがまとめられた「DXレポート」はなかなか刺激的な内容ですが、これまでお客さまのシステムをスクラッチ型で開発してきた私自身は複雑な心境です。というのは、これまでのシステム開発はお客さまのご要望をしっかりお聞きして、できる限り応えるのが基本で、プログラムを改修する場合にも、お客さまから「できるだけコストを抑えてほしい」といった要求に応える形で取り組んできました。
その積み重ねが日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を阻む障害になっているというご指摘を受けたことで、もっとこうしておけばよかったと反省する部分と、今からでもお客さまのビジネスに貢献できるようにあらためて取り組みたいという、両方の思いを持ちました。
中野あのレポートが生まれた背景には、DXに取り組む日本企業の皆さんを支援したいという強い気持ちがありました。経済産業省としては、3年ほど前からDXを推進すべく旗を振ってきましたが、実際には多くの企業が踏み出せずにいました。
いろいろな方にお話を伺っている中で、DXに成功した企業の方は「社運を懸けて既存システムを刷新するプロジェクトに成功したからDXに踏み出すことができた」と言うんですね。聞いてみるとどの企業も古いシステムを抱えていて、それがDXの推進を阻んでいると分かりました。
ただ、それは過去の間違いだとは思っていません。むしろITが技術的に未熟だった時代から日本企業が積極的にIT化に取り組んだ結果だと思っています。
金澤確かに大変な苦労をしながら、その当時の最新技術や開発手法を駆使してシステムを開発してきました。そのシステムが巨大化・複雑化し、レガシーシステムになりましたから、「刷新」といっても簡単にはいきません。DXを阻む要因になっていると思います。
相手への気遣いが複雑なシステムに

経済産業省 製造産業局
参事官(デジタルトランス
フォーメーション・イノベーション担当)
(併)ものづくり政策審議室長
中野 剛志
Takeshi Nakano
中野調べていて刷新を阻む要因が4つあることが分かりました。第1にコストが高いこと。大企業であればあるほどコストがかかります。何百億円にもなる。第2に、時間もかかる。5年や10年かかるかもしれない。第3には、コストも時間もかかる上に失敗するリスクがある。失敗してITベンダーと訴訟問題になっているケースもあります。
そして第4は、これを理解するのが難しかったのですが、新しいシステムを入れることは業務のやり方を変えることになることです。これまで業務プロセスに合わせてシステムを変えてきたわけですが、新しいシステムはそうではない。システムに合わせて業務のやり方を変える必要がある。例えて言うと、靴に合わせて足の大きさを変えなければならないのです。そうなると情報システム部門だけで判断できることではありません。経営者の決断が必要になります。
金澤Fit to Standardという考え方ですね。新しいシステムには今の業務のやり方とは相いれない部分があって、それが大きな障害になることもあります。ただ、そこには日本独特の文化的な特質もあると思います。
これまで私たちがお客さまの求めるシステムを開発してきたように、情報システム部門も使う人にとって優しいシステムにしたいと考えています。そんな相手を気遣う心が個別仕様のシステムづくりに反映されてしまったのだと思います。
中野もう1つ別の側面もあります。米国ではITエンジニアの7割がユーザー企業にいるといわれています。ソフトウェアの改修なども自分たちでやってしまいます。一方、日本は全く逆でベンダー企業に7割いて、ユーザー企業には3割しかいません。エンジニアが少ないために、どうしてもベンダーに丸投げしてしまいがちです。
裏を返すと、サービスが良くて信頼できるからこそ、アウトソースしたほうがよいという合理的な判断が働いていたわけです。ただ、依頼を受けるほうはむちゃな要求でも何とか応えようとします。その積み重ねが建て増しされて複雑になった大きな旅館のような、今の状況をつくり出してしまったと考えています。
刷新プロジェクトは人材育成のチャンス
金澤良かれと思ってやってきたことが「部分最適」といわれるような今の状況につながったのは確かです。ただ、大事なのはこれからどうするか、ということです。
中野まさにその通りです。民間企業が手を抜いていたことで起きた問題であれば、役所としては「自分で責任を取ってください」と言うしかありませんが、決してそうではありません。良かれと思って一生懸命取り組んできた結果なのです。
それが原因でDXに追随できないのであれば、役所としてできることはやっていこうと考えました。その1つが今回のDXレポートです。「2025年の崖」という言葉だけがセンセーショナルに受け止められましたが「崖を飛び越えて次に進んでほしい」というのが私たちの思いです。
金澤その思いは十分伝わってきますし、ユーザー企業のトップ層にも響いていると感じています。経済産業省がムードづくりをしてくれたことで、私たちもやりやすくなりました。
それを受けてご提案しているのが、一気にDXを進めるのではなく、3つのステップに分けて推進していくことです。
第1段階ではレガシーシステムを含めたITシステムの整理を行います。肥大化したシステムの不要な機能を縮小、あるいは廃棄します。更新頻度の少ないシステムは塩漬けにして、頻繁に更新がある領域では機能分割や刷新を検討し、新しい領域はレガシーシステムの外側のクラウド上に機能を追加します。
第2段階は、SoR(System of Record)の維持とSoE(System of Engagement)のエンハンスです。SoRは従来の業務領域をカバーするシステムであり、競争力への影響度が低い領域については、できるだけ標準的なものに合わせて効率化すべきです。一方のSoEは、システムの頻繁な変更や機能追加があります。短期間で開発することが大きなテーマであり、ローコード開発が有効です。
そして最後の第3段階では、当社が長年にわたって注力してきた、画像解析や言語処理、数理技術などを活用して、デジタルを駆使したイノベーションを実現します。このように3段階に分けたグランドシナリオが必要であると考えています。
中野確かに古いシステムを刷新してDXを推進するのには、時間がかかるかもしれません。しかし、その先には素晴らしい景色が開けていると思うのです。そのためには、ユーザー企業が主体性を持って取り組むことが大きな鍵になります。
よくユーザー企業の方からは「システム刷新をやろうとしても人材がいない」という声を聞きますが、業務革新を伴うシステム刷新をやろうとすれば情報システム部門だけではできません。そこで各部門やIT子会社から人を集めることになり、これが将来に向けた大きな力になっていきます。
実際にシステム刷新を断行した企業では、人を集めて特別チームをつくったそうです。そこにはITが分かっていて業務が分かっていない人と、業務が分かっていてITが分かっていない人が混在していましたが、業務とシステムの変革を議論しているうちに、お互いの業務を知り、企業全体としてのITリテラシーが大幅に向上したそうです。
既存システムの刷新という一大プロジェクトは単なるコストではなく、企業全体を変える活動であり、デジタル人材を育成するチャンスなのです。
金澤システム刷新というプロジェクトを意味あるものにするためにも、できるだけ早く取り組むほうがよいと思います。着手が遅れるほど費用もかさんできます。しかも、全社的な取り組みですから、ベンダーだけでは進められません。成功の秘訣はお客さまが本気で踏み込んでくれることです。そのためには経営者の覚悟が必要です。
現状では、大手企業の間でも経営者のシステムへの温度差はさまざまです。そのため、経営者の覚悟やシステムへの理解、全社的な取り組みを推進できる組織体制づくりなど、ベンダーだけでは進められない部分の話をお客さまにしています。
新しいITの世界でも日本の強みが生かせる
中野システムを刷新することで、得られるメリットはいろいろあります。例えば、最近注目されるアジャイル開発などももっと活用できるようになります。これは日本のものづくり現場にもともとあったワイワイガヤガヤのやり方にちなんでいるとか。この手法は日本企業には合っている気がしています。
金澤アジャイル開発であれば、スモールスタートもできて、変更にも柔軟に対応できます。当社では、ビジネス部門とIT部門間に存在する経験や意識のギャップを解消するためローコード開発プラットフォーム「Web Performer」を提供し、アジャイル開発をサポートしています。
中野アジャイル開発は雇用形態から見ても日本にぴったりだと思います。さまざまな職種の人が職掌を超えて意見を出し合っていきます。これは専門性に特化した雇用形態の国にはなじみません。日本企業の強みが生かせる手法です。
金澤新しいITの世界でも日本の強みが生かせるということですね。加えて、日本企業がDXを進めるということは、消費者の利便性や利益が高まり、少子化による労働力不足や環境破壊といった社会問題の解決の解につながるかもしれません。
中野一度全部をデジタル化してしまえば、後はかなり楽になるはずです。
見逃せないのは、ITの使い勝手が良くなって、ITが人間のほうに寄ってきてくれていることです。しかも製造業で働く人たちはもともとITにはなじみもありますし、今はデジタルに慣れたデジタルネイティブの社員も増えています。「2025年の崖」の先には日本企業の強みを生かせる世界が広がっているのです。
金澤中野さんがおっしゃるように、崖を飛び越えれば新しい世界が開けます。今後、子供の頃からスマホを手にしてきた世代が社会に出て活躍する時代が来ます。彼ら彼女らの感性がどんなビジネスモデルを打ち出し、どんなUI/UXを創造し世の中を変えていくかはとても楽しみです。今の経営層の世代は、新しい人たちの感性を生かせるような経営の仕組みや教育環境を整えていく責任があり、一方でビジネスを維持・向上させていくことも必要です。デジタル人材の不足などでDXを進めにくい企業にとっては、厳しい時代になる事が予想されますが、その中でも生き残れるようなサポートをITをもって考えるのが、われわれITベンダーの役割の1つであると考えています。本日は、どうもありがとうございました。

1971年生まれ。1996年東京大学教養学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。2005年英エディンバラ大学から博士号(政治思想)取得。経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課長などを経て、2019年7月から製造産業局参事官(デジタルトランスフォーメーション・イノベーション担当)(併)ものづくり政策審議室長。

1959年生まれ。1992年住友金属システム開発(現キヤノンITソリューションズ)入社。2015年に執行役員SIサービス事業本部開発統括センター長。2016年に上席執行役員SIサービス事業本部長。2017年に取締役。キヤノンマーケティングジャパン執行役員(現任)。2018年に常務執行役員。2019年3月に当社の代表取締役社長に就任。
※ 記事中のデータ、人物の所属・役職などは、記事掲載当時のものです。