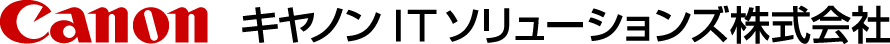IoTの成否を左右する「PoC」の重要性
- 特集
試行錯誤を重ね未知の分野を切り拓け
最近、システム開発の初期段階でPoC(Proof of Concept:概念実証)による検証工程を取り入れるケースがにわかに増えている。とりわけPoC実施の重要性が高まっている分野が「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」である。ただ、PoCによる事前検証には相当な時間がかかる。経験の少ない分野へのチャレンジだけに必ずしも成功するとは限らない。そうした前提に立って、長期的な視点でPoCに取り組む必要がある。数多くのIoTプロジェクトに関わってきた東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之氏に、IoT実践に向けたPoC実施のポイント、経営者やビジネス現場、エンジニアに求められる姿勢などについて聞いた。
デジタルの潮流があらゆる産業を変える

東京大学大学院
工学系研究科教授
森川 博之 氏
Hiroyuki Morikawa
近年、IoT関連のプロジェクトがさまざまな企業で増えている。まずはプロトタイプをつくって、限られたエリアで試してみる。そんなPoCを複数走らせている企業も少なくない。IoTをはじめAIやビッグデータなどの先端技術を用いたPoCを数多く手掛け、産学連携の実績も豊富な東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之氏は、現状を次のように見ている。
「2016年から2017年ごろ、多くの企業でIoTプロジェクトが次々に立ち上がりました。いろいろなところで話題になったことで経営者が興味を持ち、『うちでも何かやろう』と部下に指示したのでしょう。しかし、IoTには試行錯誤がつきものですし、成果を上げるにはそれなりの時間がかかります。短気な経営者なら、『半年もたったのに、まだ結果が出ていない』としびれを切らしてしまうかもしれません。当初の期待値が高すぎて、『この程度か』と受け止められてしまうケースもあるでしょう。思い通りの成果を上げたPoCは、必ずしも多くないと思います」
実際、華々しく打ち上げたIoTプロジェクトが、尻すぼみに終わったケースも少なくないようだ。森川氏はこう続ける。
「大半のIoTプロジェクトは未知への挑戦です。やってみなければ成功するかどうかは分かりません。PoCに取り組んだものの、撤退することもあるでしょう。そのときには、他のアイデアを議論して別のテーマにチャレンジすればいい。そうして“数撃つ”ことが大切です。1度や2度の失敗で、『うちではムリだ』と諦めないでほしい。今年から来年にかけては、経営者の覚悟が問われる正念場だと思います」
今は、アナログからデジタルへの過渡期である。企業内にはデジタルに詳しい社員、それほどではない社員が混在しているはずだ。デジタルトランスフォーメーションを目指すと宣言しても、現場からいいアイデアが出てこないケースもあれば、業務プロセスを変更することに抵抗感があって前に進まないこともあるだろう。それでも、デジタル化の潮流が不可避であるとすれば、企業には腰を据えた取り組みが求められる。
「デジタル技術は汎用技術です。蒸気機関や電力と同じように、社会とビジネスに極めて大きな影響を与えるでしょう。かつて、すべての工場の動力が電力で代替されるまでには数十年かかりました。インフラや働き方などを一気に変えることができないからです。デジタルも似たところがあります。今すぐではないとしても、デジタルはあらゆる産業を、いずれ大きく変えてしまうはずです」(森川氏)
幅広い産業分野の企業にデジタルが定着するまでには、長い時間がかかる。これまでのITへの取り組みは「前哨戦のようなもの」と森川氏は考えている。今はデジタルの時代が幕を開けたところ、“フェーズ1”が始まったばかりだ。これから切り拓かれるであろうデジタルのフロンティアは広大である。
IoTのヒントは身近なところに埋もれている
デジタル化のフェーズ1という段階ながら、すでに世界中で成功事例が報告されている。森川氏が挙げたのがドイツの工作機械メーカーである。同社はオンラインストアでアプリケーションを提供している。アップルの「App Store」やグーグルの「Google Play」と同じようなサービスを、工場で働く人たちに提供している。
「工作機械を操作するためのソフトウェアを、ユーザーはECサイトからダウンロードして使います。この話を聞いたとき、意表を突かれました。理にかなったサービスですが、正直に言えば、私自身にはそのような可能性を想像することができなかった。なぜかというと、アップルやグーグルなどのイメージが強かったからです。『アプリケーションストアは消費者向け』という先入観があり、工作機械の並ぶ工場とアプリケーションストアが結び付かなかったのです」(森川氏)
工作機械に限らず、今や多くの設備や機器がソフトウェアで動いている。そして、ソフトウェアの役割は大きくなる一方だ。同じようなサービスが、これからも次々に登場することだろう。
IoTの取り組みの中には、「なぜ、今まで気づかなかったのだろう」と思うような成功事例が少なくない。上記のアプリケーションストアもそうかもしれない。また、2011年に四国で始まった古紙回収の仕組みに森川氏は注目しているという。
「身近の課題を解決する小さな事例です。やったことは地場スーパーの敷地に、重量センサーとSIMカードでスマート化した古紙回収箱を設置しただけ。回収された古紙の重量を遠隔で把握できるので、回収事業者は適切なタイミングでトラックを派遣することができます」
古紙回収事業者はトラックの運行を最適化して、回収コストを大きく低減させた。低減分の一部はポイントとして、古紙を持ち込んだ消費者に還元する。一方、場所を提供するスーパーでは、消費者の来店頻度が高まったという。古紙回収事業者とスーパー、消費者の三者すべてにメリットがある。
愛媛県四国中央市のスーパーで小さくスタートした仕組みは大きく成長し、すでに九州や本州のスーパーを含めて数十店が参加するまでになった。この場合、最初の店舗での取り組みがPoCに当たる。ここで顧客や店舗から好評を得たことで、他のスーパーへの展開が可能になった。小さな成功を実証することは、PoCの重要な役割といえる。
このスキームの特徴の1つは、初期コストが非常に低いことだ。ランニングコストはネットワークの費用程度で、トラック運行コストの削減分で十分カバーすることができる。大企業であれば、おそらく部門予算で実行できる程度の取り組みだろう。
現場と技術者との信頼感に基づく連携が重要
さまざまなモノをIoTでつなぐためには、組織間の連携も欠かせない。自前のリソースだけで対応できるプロジェクトもあるだろうが、それでは大きな価値の創出は難しいかもしれない。より大きな価値を生み出すためには、多くのプレーヤーを巻き込む必要がある。
まず、テクノロジーの専門家とのパートナーシップである。
「社内に技術者集団を抱えている企業もあるでしょうが、多くの場合、ITベンダーなどテクノロジー企業との協力は不可欠でしょう。ビジネス側とテクノロジー側が一緒に悩み考えながら、物事を進めていく必要があります」(森川氏)
プロジェクトを立ち上げた当初、ビジネス側にはデジタルの知識、テクノロジー側にはビジネスの知識が不足しているはずだ。森川氏は「お互いに歩み寄る姿勢と信頼感が大切」と強調する。例えば、森川研究室は建設会社と一緒に、IoTを用いて橋のモニタリングに関するプロジェクトを進めているという。
「そもそも、お互いに信頼を持てなければプロジェクトが始まらなかったでしょう。今、私たちは土木を、橋の専門家たちはIoTなどのデジタルを学んでいます。お互いにリスペクトし合いながら学ぶことで、参加メンバーが共通言語で議論する土壌が生まれます」(森川氏)
IoTプロジェクトで異業種連携は珍しくない。ビジネス側とテクノロジー側、それぞれで複数のプレーヤーが参加することもある。これらの参加する企業とメンバーの意識は極めて重要と森川氏は指摘する。
「企業間の連携は、同じ業界内でも容易ではありません。異業種連携となれば、なおさらです。プロジェクトを円滑に進めるためには、信頼感とか仲間意識に加えて、利他の精神や共感力といったものが大事だと思います。『自分たちだけもうけよう』ではなく、互いにメリットを得られるようなモデルをつくる。この点を、常に意識しておく必要があると思います」
また、メンバーが同じ方向を目指すためには、目的の明確化も大切だ。何のためにやるのか、どういう価値を創出したいのか。こうした目的を共有した上で、走りながら考える必要がある。
「目的は1つではないかもしれませんし、途中で変わるかもしれません。それをチームが一緒に考えながら共有する。つまり、走りながら考え続けることです。走っているうちに想定しなかった課題にぶつかったり、当初は思いつかなかったアイデアが出てきたりすることもあるでしょう。工夫や修正を重ねて一つひとつのハードルを乗り越え、みんなでゴールを目指すのです」と森川氏。その際、撤退についても念頭に置くべきと付言する。
「まったく新しいチャレンジですから、失敗の可能性が高い。では、どういう状態になったときに撤退するか。そのルールは事前に定めておくべきでしょう。特に日本企業の場合、撤退が不得意といわれます。事前にルールを明確にしておけば、成算のないPoCをいたずらに長引かせるようなことは避けられると思います」
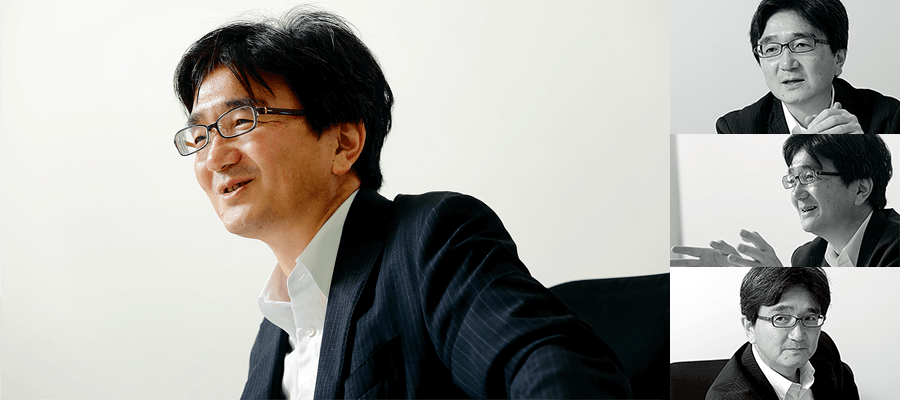
PoCに取り組むチームは「海兵隊」
それぞれが得意技を持つメンバーで構成され、信頼感で結ばれたチームによるチャレンジ。そんなプロジェクトチームを、森川氏は「海兵隊」に例えて説明する。そこには2つの意味が込められているという。
「第1に、コンパクトな組織とフットワークの軽さが重要です。何が起きるか分からないので、俊敏に動ける小規模なチーム編成とすべきでしょう。第2に、海兵隊は最もリスクの高い戦場で戦うチームです。許容限度を超える危険があると分かれば、中止や撤退の判断が求められます。PoCも同じ。これまで経験したことのない危険な場所で戦うのですから、失敗の可能性を常に意識しておかなければなりません」
失敗というとネガティブな響きがあるが、それは新しい学びとノウハウ蓄積の機会。試行錯誤を経て学ぶたびに、成功に近づくことができる。
森川氏の言うリスクの高さこそ、IoTやAIなどの分野でPoCアプローチが求められる理由だ。リスクが無視できるほど低ければ、多くの人員を擁する事業部門が手掛けることもできるだろう。しかし、不透明、不確実が前提であれば、小規模なチームで試してみるほかない。森川氏は「成功確率の低い分野では、PoC以外のアプローチは考えられません。ただ、それが成功した場合には、大きな価値創造につながります」という。
IoTだけでなく、ビジネスのデジタルシフトに関わるさまざまな分野でPoCの手法が用いられている。一方で、「今のビジネスが好調だから」と、PoCに消極的な企業もある。こうした企業に対する森川氏のメッセージは次のようなものだ。
「『両利きの経営』という言葉があります。『知の深化』と『知の探索』の両方をバランスよく追求する経営スタイルです。知の深化は既存ビジネスを磨くことですが、それだけで将来にわたって成長し続けることはできないでしょう。自分たちがよく知らない領域でも、ビジネスの種を見つけるような知の探索に取り組むことが重要。それが、中長期的な成長につながります。PoCはそんな活動の一環として、今や経営にとって欠かせない手段だと思います」
PoCを適用すべき分野は新事業創出かもしれないし、サービスモデルの刷新、あるいは業務プロセスの変革かもしれない。異業種との交流で初めて気づかされることもあれば、身近なところに埋もれている意外なアイデアもあるだろう。まずは、一歩を踏み出してPoCに取り組むカルチャーを醸成すること。それがチャレンジの機運を高め、やがて大きな果実をもたらすことだろう。
工学博士。1992年3月東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。2007年4月東京大学先端科学技術研究センター教授、2017年4月から現職。「社会基盤のICT」「エクスペリエンスとしてのICT」の視点から、ビッグデータ、IoT、センサーネットワーク、モバイル通信システムなどに関する研究を続けている。
※ 記事中のデータ、人物の所属・役職などは、記事掲載当時のものです。